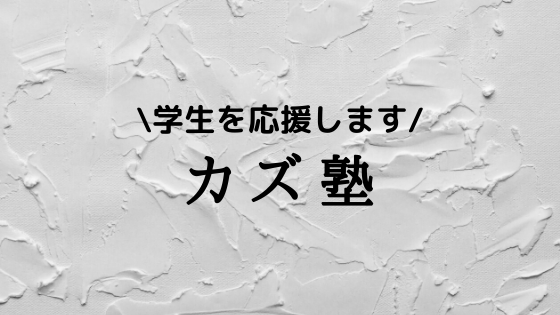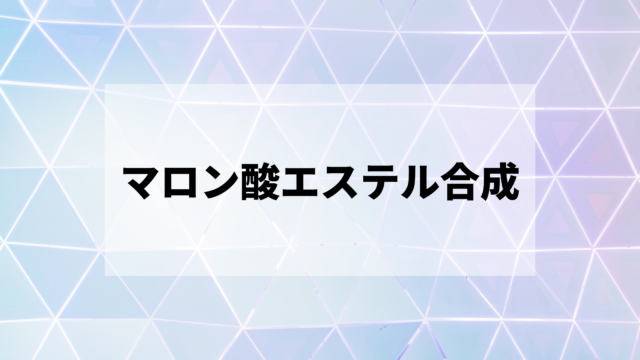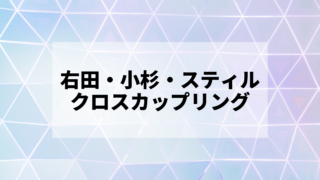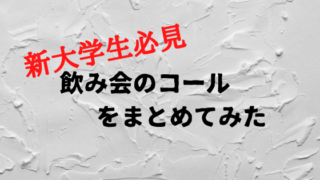アルドール反応とは、有機化学において炭素-炭素結合を形成し、新たにβ-ヒドロキシカルボニル化合物を生成する反応である。これらの生成物は、アルデヒド+アルコールからアルドールとして知られており、多くの生成物に見られる構造的モチーフである。アルドール構造単位は、天然物であれ合成物であれ、多くの重要な分子に見いだされる。例えば、アルドール反応は、汎用化学品であるペンタエリスリトールの大量生産や心臓病治療薬リピトール(アトルバスタチン、カルシウム塩)の合成に用いられている。
アルドール反応は、比較的単純な2つの分子を結合して、より複雑な分子にするものである。複雑さが増すのは、最大で2つの新しい立体中心(アルドール付加体のα-炭素とβ-炭素上、下のスキームではアスタリスクで表示)が形成されるからである。現代の方法論は、アルドール反応を高収率で進行させるだけでなく、これらの立体中心の相対配置と絶対配置の両方を制御することが可能である。このように特定の立体異性体を選択的に合成できることは、立体異性体が際立った化学的・生物学的特性を持つ可能性があるため、重要である。
例えば、立体異性体であるアルドール単位は、生物界に存在する分子の一種であるポリケチドに特に多く存在する。自然界では、ポリケチドは酵素によって合成され、反復的なクライゼン縮合を起こす。この反応による1,3-ジカルボニル生成物を様々に誘導体化することで、多種多様な興味深い構造を作り出すことができる。このような誘導体化では、カルボニル基の1つを還元して、アルドール基を生成することが多い。これらの構造の中には、免疫抑制剤のFK506、抗腫瘍剤のディスコデルモライド、抗真菌剤のアンフォテリシンBなど、強力な生物学的特性を有するものがある。このような化合物の多くは、かつては合成がほとんど不可能と考えられていたが、アルドール法による効率的な合成が可能になり、多くの場合、合成が可能になった。
現代の典型的なアルドール付加反応は、上図のように、ケトンのエノラートをアルデヒドに求核付加させるものである。いったん生成したアルドール生成物は、時に1分子の水を失ってα,β-不飽和カルボニル化合物を形成することがある。これをアルドール縮合という。アルドール反応には、ケトン、アルデヒド、その他多くのカルボニル化合物のエノール、エノラート、エノールエーテルなど、様々な求核剤が使用されることがある。求電子的なパートナーは、通常、アルデヒドまたはケトンである(マンニッヒ反応のような多くのバリエーションが存在する)。求核剤と求電子剤が異なる場合は交差アルドール反応、逆に求核剤と求電子剤が同じ場合はアルドール二量化反応と呼ばれる。
概要
- 炭素-炭素結合を生成する
- 生成物の官能基や不斉炭素をコントロールしやすい
- 原子効率が高い

歴史
1869年にロシアの化学者Alexander Borodinが、1872年にフランスの化学者Charles Adolphe Wurtzがそれぞれ発見し、2つのカルボニル化合物(当初の実験ではアルデヒドを使用)を結合させた。
反応機構
アルドール反応は、2つの異なるメカニズムで進行することがある。アルデヒドやケトンなどのカルボニル化合物は、エノールやエノールエーテルに変換されることがある。これらの種はα炭素に求核性があり、プロトン化アルデヒドのような特に反応性の高いプロトン化カルボニルを攻撃することができる。これが「エノール機構」である。カルボニル化合物は炭素酸であるため、脱プロトン化されてエノラートを形成することもある。エノールやエノールエーテルよりもはるかに求核性が高く、求電子物質を直接攻撃することができる。ケトンは反応性が低いので、親電子物質としては通常アルデヒドが用いられる。これが「エノラート機構」である。
アルドール多様体の魅力にもかかわらず、このプロセスを触媒的に有効なものにするためには、いくつかの問題がある。まず、熱力学的な問題であるが、ほとんどのアルドール反応は可逆的である。さらに、単純なアルデヒド-ケトンアルドール反応の場合、平衡もギリギリ生成物側にある。条件が特に厳しい場合(例:NaOMe/MeOH/還流)、縮合が起こることがあるが、これは通常、穏やかな試薬と低温(例:LDA(強塩基)、THF、-78℃)で避けることが可能である。アルドール付加は通常不可逆的な条件下でほぼ完全に進行するが、単離されたアルドール付加体は塩基によるレトロアルドール開裂に敏感で、出発物質を戻すことができる。一方、レトロアルドール縮合は稀ではあるが可能である。これは、自然界に存在するクラスIアルドラーゼの触媒戦略や、多くの低分子アミン触媒の基本である。
実験手順
更新をお待ちください
実験のコツ
応用例
更新をお待ちください
参考文献
関連書籍