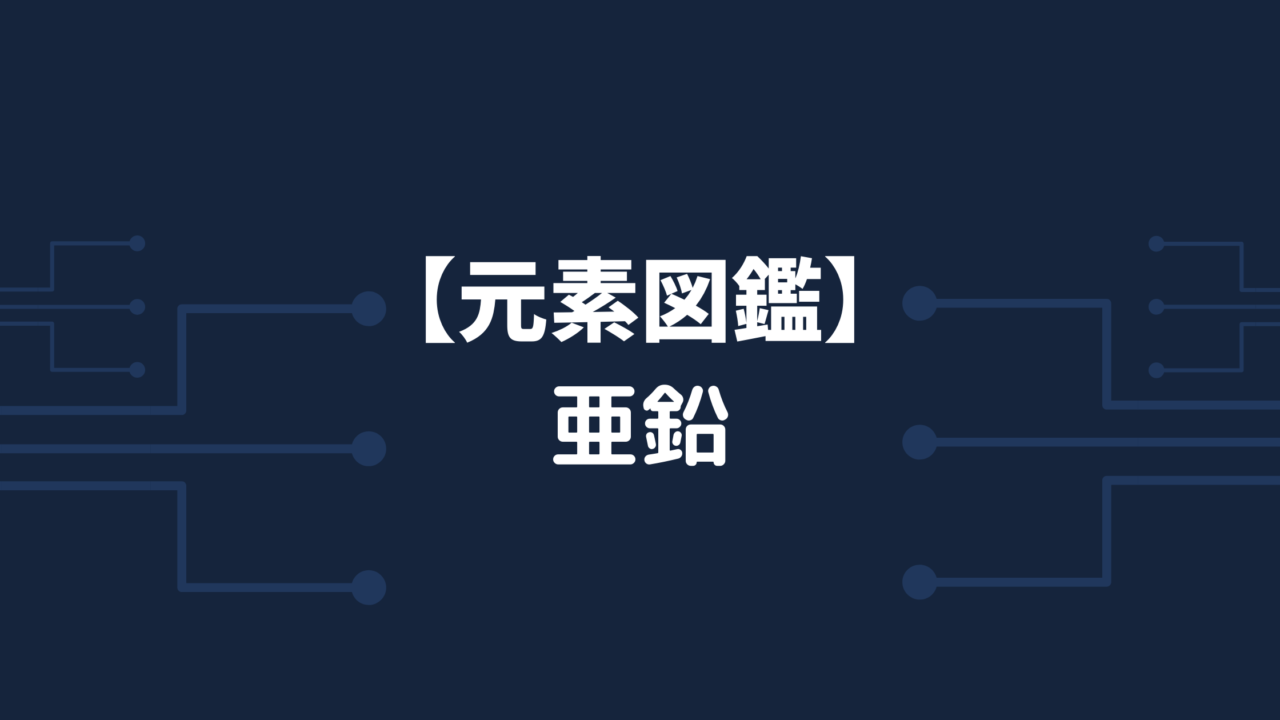亜鉛に関する情報をまとめました。
亜鉛の基本情報
| 和名 | 亜鉛 |
|---|---|
| 英名 | Zinc |
| 語源 | ドイツ語「櫛やフォークの歯(Zinke)」 |
| 元素記号 | Zn |
| 原子番号 | 30 |
| 原子量 | 65.38 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 青白色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 7.135 g/cm3(20℃) |
| 融点 | 419.58℃ |
| 沸点 | 907℃ |
| 発見者 | マルクグラフ(ドイツ)[1746年] |
| 含有鉱物 | 閃亜鉛鉱 |
亜鉛の主な特徴
- 遷移後元素で、周期表第12族に属す
- 銀白色の金属であり、空気中では安定ながら加熱や酸により容易に酸化される
- 電気伝導性は銅や銀より劣りますが、耐食性と化学的安定性を活かして、防錆や合金材料として広く利用される
- 生体必須元素であり、100種以上の酵素の構成金属として重要
亜鉛の歴史
発見
金属亜鉛は古代インド(紀元前1000年頃)で製錬されていた記録がありますが、
ヨーロッパでの本格的な製造は16世紀以降に始まりました。
1746年、ドイツの化学者アンドレアス・マルグラフが金属亜鉛の純粋な製法を確立しました。
名前の由来
「亜鉛(Zinc)」という名は、ドイツ語の “zinke”(突起、歯)に由来するとされ、
これは亜鉛の結晶が針状に成長することに由来しています。
亜鉛の主な用途
亜鉛は防錆・合金・電池・健康食品など多方面で利用されています:
- 防錆用途: 鉄の表面に亜鉛を被覆する溶融亜鉛めっき(トタン)が広く使用
- 合金: 真鍮(Cu-Zn)、亜鉛ダイキャスト、アルミ-亜鉛合金など
- 電池材料: 乾電池(Zn-MnO₂)、空気亜鉛電池、水素発生電極
- 化粧品・医薬品: 酸化亜鉛は日焼け止めや軟膏などに使用
- 栄養補助: 亜鉛は味覚や免疫調整に関与し、サプリメントとしても普及
亜鉛の生成方法
亜鉛は主に閃亜鉛鉱(ZnS)などから以下の手法で製造されます:
- 乾式法(ロースト法): ZnSを焼成してZnOに変え、炭素で還元して金属亜鉛を得る
- 湿式法: 酸でZnを溶出し、電解により高純度金属を得る
- 副産物: 銅鉱や鉛鉱の精錬過程で副産物として得られることもある
亜鉛を含む化合物
亜鉛は主に+2の酸化数で安定な化合物を多数形成します:
- ZnO(酸化亜鉛): 白色粉末。日焼け止め、セラミック、ゴム補強材
- ZnCl₂(塩化亜鉛): 助溶剤や脱水剤として使用
- ZnSO₄(硫酸亜鉛): 肥料・微量栄養素・医薬品に利用
- 亜鉛錯体: 4配位で安定な錯体を形成し、触媒や酵素モデルとして研究される
リチウムに関わる研究事例
亜鉛は電池材料、生体内反応、環境化学など多くの分野で研究されています:
- 次世代電池: 亜鉛空気電池やZn-イオン電池の開発
- 生体内の亜鉛酵素: カルボン酸脱水酵素やDNAポリメラーゼの活性中心
- 味覚研究: 味覚受容体における亜鉛の役割と欠乏症との関係
- 抗菌材料: 酸化亜鉛ナノ粒子の抗菌性を利用した塗料・繊維開発
- 錯体触媒: 有機合成における亜鉛錯体の触媒機能(例:エポキシ化反応)
参考図書
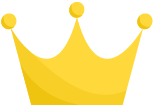 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
リンク
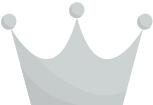 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
リンク
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。
リンク