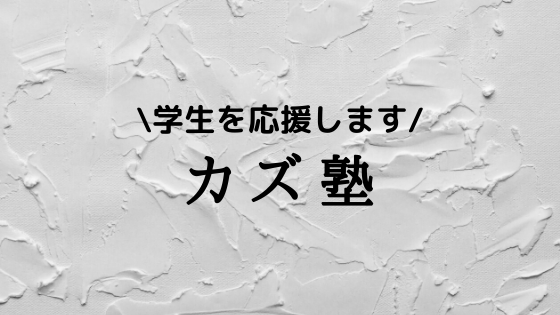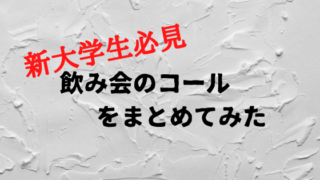文献情報
タイトル:Isolation and Proof of Structure of Wildfire Toxin
著者:Walter W. Stewart
基本情報:Nature (London), 1971, 229, 174-178.
受領日:1970/11/16
出版日:1971/01/15
DOI:10.1038/229174a0
概要
20年来、野火の毒素はその不思議な生物学的・化学的特性から注目されてきた。今回初めて報告されたその構造は、数少ない天然由来のβ-ラクタム系化合物であることから、その作用機序を知る手がかりとなりそうだ。
日本語訳
タバコの山火事(WILDFIRE)は、毒素を媒介とする植物病の中で、おそらく最も徹底的に研究された病害である。しかし、20年にわたる野火病の毒素の化学的、生化学的研究によって、その構造は明らかにされなかった。
このような事態を招いたのは、野火の毒素が著しく不安定で、容易に生物学的に不活性な化合物に異性化するためである。この不安定性が不純な毒素の単離を招き、初期の化学的データの解釈を狂わせることになった。ここでは、純粋な野火の毒素を単離する2段階の方法、毒素の化学的性質、および化学構造の提案(図1)を報告する。
問題の歴史
ワイルドファイアは、タバコの葉に発生する非常に感染力の強い病気です。この病気は、タバコ畑を急速に破壊的に広がることからその名がついた。1917年にノースカロライナ州で初めて報告され、すぐにタバコに影響を与える最も破壊的な病気として認識されるようになった。この病気は経験則に基づく対策によって防除され、もはや経済的な重要性はないが、科学的な関心は高まり続けている。
野火病に罹患した植物では、葉が1cmほどの円形の黄色い病斑で覆われる。これらの葉緑素病斑の中心部から、感染の原因菌であるPseudomonas tabaciを分離し、in vitroで培養することができる。無細胞培養の濾液を用いると、健康なタバコ(あるいは他のほとんどの植物種)の葉に濾液を接種すると、野焼きに特徴的な円形の黄色い病斑が再現される3(Fig.2)。このことから、野火病の顕著な兆候は外毒素によって引き起こされることが示唆された。
野火の毒素に関する体系的な研究は、Woolley と Braun が率いるチームが毒素の測定と濃縮の方法を開発した 1950 年代初頭に始まった4。この研究は、毒素が不安定であったために妨げられたものの、その後のこの分野におけるすべての研究の基礎となった。
Woolleyらは、精製した毒素の化学反応から、a-lactylamino-J3-hydroxy-e-aminopimelic acid lactoneを山火事毒素の構造として提案した(図3)5。 その後の研究6-8により、この構造提案は否定されたが、この構造は広く受け入れられ、最近の文献に引用されるようになった。
過去10年間、野火の毒素に関する研究は、その作用機序に焦点が当てられてきた9 -10. この毒素は、バクテリア、藻類、高等植物、哺乳類など、多種多様な生物に対して高い毒性を示すll – 12 ; 0.05 Ilgでタバコの葉に2mmの病斑ができる。その毒性は、多くの生物でグルタミンによって、また一部の生物ではメチオニンによって完全に逆転する13。代謝阻害剤としてよく研究されているメチオニン・スルホキシミンと作用様式に多くの類似性がある。例えば、野火の毒素は、メチオニン・スルホキシミンと同様に、グルタミン合成酵素の強力な阻害剤であるという予備的な証拠がある14.15。野火病の毒素の作用機序に対する関心は依然として高く16、その構造の明確な決定が必要であることは明らかである。
Wild Toxin の単離
Pseudomonas tabaci(分離体Pt3、International Collection of Phytopathogenic Bacteria, Davis, Californiaから)をWoolleyの培地で25℃、撹拌と激しい通気で15 I. バッチで増殖させた4. 生産と分離の間、毒素の含有量は自動アミノ酸分析および葉のバイオアッセイによってモニターされた8。培養液は通常、接種後3日目に回収した。毒素の単離のために、30回分の無細胞濾液をpH2.5に酸性化し、pH2.5に調整した1 M NaCIで平衡化した「Dowex AG-50W X2」樹脂(50-100メッシュ)の4 kgカラムに通した。毒素はpHの変化とともに約I液量になり、これをプールして凍結乾燥させた。このステップにより、典型的には30倍の濃縮(凍結乾燥前)と200倍の精製が行われた。粗毒素は約35重量%の純度で得られ、全体の収率は85〜95%であった。
粗毒素の半分を、pH3.1の0.2Mピリジン-酢酸バッファーを用いた「Dowex AG-50W X2」(200-400メッシュ)の7.5 x i25cmカラムでの4°Cでのクロマトグラフィーによってさらに精製した。生物活性の99%以上は単一のピークに現れ、それは明らかに非対称であった*。このピークの前半をプールして凍結乾燥すると、約200 mgの純粋な野火の毒素が、ふわふわしたオフホワイトの粉末として得られた。何度試みても、この毒素を結晶化することはできなかった。
毒素の化学
野火の毒素の特性およびその純度の証拠は、クロマトグラフィー、微量分析、ペクトラル法、およびより安定な化合物への分解によって得られた。Spackman, Stein and Moore17 の方法に従って自動アミノ酸分析装置で毒素をイオン交換クロマトグラフィーで分析したところ、通常アラニンが占める位置に単一の対称的なピークが認められた。この微量不純物は、後に毒素の分解生成物であることが示され、その特性については後述する。Wildfire 毒素は、3つの異なる溶媒系での薄層クロマトグラフィーで単一のスポットを示した。電気泳動では、この毒素はpH 5.0で中性種として移動することが示された。100℃で3時間乾燥させた試料の微量分析では、CllH19N306に相当する値が得られた: found, C, 45.30; H, 6.78; N, 14.19; ash, 0.3%; loss on drying, 4.2%; CllHl9N306 requires C, 45.67; H,6.62; N,14.53. この毒素の溶液は可視域には吸収がなく、紫外域にわずかに吸収があるのみであった。赤外分光法では,3,400-3,250cm-Iにブロードバンド,1,740, 1,670, 1,600cm-I に3つの分解カルボニルバンド,1,380, 1,205, 1,075, 1,000, 975, 940cm-1にバンドが見られた。
図4はそのスペクトルと各信号の割り当てを示したものである。中性および塩基性条件下でスペクトルに生じた変化から、毒素中の滴定基の位置が決定された。8= 1.23, 8:::2.1, 8::.3.4 のシグナルの位置は,中性条件下でも塩基性条件下でも変化しなかった。3.4はpHの影響を受けず(8はp.p.m.の化学シフト)、これらのシグナルは12個の炭素結合プロトンのうち9個を占めている。残りのスペクトルは、8 = 4.24の1プロトン三重項と8::.4.5の2プロトン多重項であった。4.5である。これらのシグナルは両方ともpH依存性であった。これらのシグナルはいずれもpHに依存する。酸および塩基におけるそれらの位置を中性における位置と比較すると、単純なパターンが明らかになった。塩基化では1-プロトン三重項が上方にシフトし(0.71 p.p.m.)、酸性化ではこの共鳴は変化しない(0.01 p.p.m.)ことがわかった。逆に、酸性化では2-プロトン多重項が下方にシフトした(C.27 p.p.m.)が、塩基性化ではその位置はほとんど変わらなかった(0.04 p.p.m.)。これらのシフトは、1-プロトン三重項がアンモニウム基の近くにあり、2-プロトン多重項がカルボン酸基の近くにあることを示しています(Sheinblattの議論と比較してください)18。
二重共鳴実験により、3つのpH依存プロトンの環境がさらに解明された。1プロトン三重項が8::.2で4つのメチレンプロトンに結合していることが示され、2プロトン多重項が8::.2でメチル基に結合していることが示された。2.0、2-プロトン多重項が8=1.23でメチル基と結合していることが示された。このメチル基を照射すると、2-プロトン多重項が4Hzの結合定数を持つAB系に縮退した。
これらのデータは、図1に示した構造と矛盾しない。この式は、毒素の様々な分解によっても支持される。加水分解により、2つのアミノ酸であるスレオニンとタブトキシニンが得られた。これらはクロマトグラフィー、分光学によって、またさらなる分解によって単離・同定された。スレオニンはクロマトグラフィーとポラリメトリーによってLs-スレオニンであることが示された。これはタンパク質加水分解物に見られる一般的な異性体である。単離した物質の赤外スペクトルは、真正のLs-threonineのスペクトルとほぼ同じであった。
タブトキシニンは、Woolleyらが毒素加水分解物19から単離したアミノ酸の俗称で、彼らが提案した構造は、その後撤回された6。7. 私の試料とWoolleyが調製した本物の試料との比較については、後述する。私が単離したタブトキシニンのマススペクトルは、m/e=207に弱いピーク(おそらく「M + I」イオン)とm/e=170に強いピーク(おそらく親イオンから2分子の水が失われることによって形成される)を示した。後者のピークの正確な質量はC7HloN203のそれに対応した(見つかった:170.1681;C7H lON 20 3は170.1691を必要とする)。タブトキシニンはpH5.0では中性分子として移動した。過ヨウ素酸塩処理(0.1 M Na104、室温、pH 4.50 で 15 分間)により速やかに破壊され、70 %の収率でホルムアルデヒドを、さらに酸化・加水分解により 25 %の収率でグルタミン酸を与えた。毒素自体は過ヨウ素酸に対して安定である(同条件で5%以下の破壊)。
スレオニンは赤堀ヒドラジノリシス20(スレオニンの収率16 %)とDakin-West分解21(スレオニンの90 %以上の破壊,部分的エピマー化タブトキシニンの67 %回収)により毒素の「C-ターミナル」であることが示された。
毒素の不活性化
野火の毒素の構造研究は、毒素の顕著な不安定性によって常に妨げられていた。室温とpH7では、毒素溶液の生物学的活性は約1日の半減期で減衰した。不活性化した毒素の溶液を化学的に調べたところ、単一の主成分が存在することがわかり、それは野火病の毒素の異性体であることが判明した。この異性体は生物学的に不活性で(野火の毒素の活性の0.1%以下)、Woolleyとその共同研究者が記載したどの化合物とも同定することができない。私は、この野火病の毒素の異性体をアイソタブトキシンと呼ぶことを提案する。この異性体の単離と特性解析は、親毒素の構造に対するもう一つの証拠となる。
wildfire toxinの溶液をpH 3.0で60分間煮沸すると95 %の収率でisotabtoxinが得られ、分取ピリジン-酢酸クロマトグラフィーでふわふわした白色の粉末として単離された。自動アミノ酸分析装置のイオン交換クロマトグラフィー(バリンとシスチンの中間に出現)と3系統の薄層クロマトグラフィーにかけると、均質な物質となった。イソタブトキシンはやや不満足な分析値を示したが、これはその吸湿性によると思われる。100℃で24時間乾燥させた試料は、次のような結果を得た。C,44.97; H,6.65; N,14.13; 灰分, 0.3%; 乾燥減量, 3.4%であった。CIIHl9N306が必要である。C,45.67; H,6.62; N,14.53. KBrペレットの赤外分光分析では,3,420-3,240 cm-lに幅広い吸収があり,1,660 と 1,600 cm-‘にカルボニルバンド,1,390, 1,310, 1,220, 1,145, 1,078 および 997 cm-lにバンドが見られた。
イソタブトキシンのNMRスペクトルは、酸性、塩基性、中性条件下で220 MHzで得られた。これらのスペクトルは野火止用毒素のスペクトルと酷似していたが、3つの顕著な違いがあった。(1)タブトキシニンのa-プロトンの化学シフト(図5参照)はpHに依存しない、(2)タブトキシニンのE-プロトンはpHに依存するようになった(塩基化により0.40ppmのアップフィールドシフトが生じた)、(3)E-プロトンの結合定数は約6Hz(wildfire toxin)から約13Hzに増加した、。
これらのデータは、イソタブトキシンが野火病の毒素の異性化によって生成されることを示している。この異性化は、4員環のラクタムのトランスラクタム化によって、より安定な6員環のラクタムが生成されるというメカニズムで容易に説明できる(図5)。イソタブトキシンの構造は、様々な分解データによってさらに裏付けられている。赤堀ヒドラジノリシスでは37%の収率でスレオニンが得られ、微量のタブトキシニンが残った。最後に,過ヨウ素酸塩をpH4.50にすると,15分間でアイソタブトキシンは99%破壊され,残渣をさらに酸化・加水分解すると,スレオニンが60%,グルタミン酸が40%の収量で得られた.
構造証明のまとめ
Fig.Iに示した構造の場合をまとめると、次のようになる。野火の毒素を加水分解すると、L,-スレオニンとタブトキシニンの2つのアミノ酸が得られる(Fig.I)。スレオニンの同一性は、天然物との比較により確立される。タブトキシニンの構造は、以下の観察から推論することができる。質量分析の結果、アミノ酸はC7H14NzOsであろうが、C7H2Nz0 4またはC7HlQNz0 3とも一致する。タブトキシニンの電気的中性、過ヨウ素酸による破壊から、ヒドロキシジアミノジカルボン酸であり、C7HI4N’lOsであることが示唆される。グルタミン酸に酸化されると、7つの炭素のうち5つが見つかり、6つ目は過ヨウ素酸酸化後にホルムアルデヒドとして検出される。これらの観察から、タブトキシニンの構造として考えられるものは、一部を除いてすべて除外される。残りの構造の選択は、無傷の毒素のNMRスペクトルに基づいて、極めて簡単に行うことができる。
すなわち、(1)毒素にはタブトキシニンとスレオニンというアミノ酸以外の成分が存在するのか、(2)これら2つのアミノ酸は毒素の中でどのように配置されているのか、という疑問である。毒素のNMRスペクトルは、炭素結合プロトンを含む断片の可能性を排除するのに有効です。観測されたシグナルはすべて、存在することが分かっている2つのアミノ酸で説明されます。微量分析値から、毒素には炭素結合プロトンを持たないフラグメント(不安定なカルボキシル基など)は存在しないことが示唆された。
したがって、この毒素はタブトキシニンとスレオニンのアンヒドロ化合物であると思われる。この2つの多官能性アミノ酸の組み合わせは、潜在的に多くの方法がある。NMRスペクトルのpH依存性から、次の5つの結論が導き出され、状況は非常に単純化される:(I)スレオニンのカルボキシル基は自由である;(2)スレオニンのアミノ基は電子吸引性の連結で結合している;(3)タブトキシニンのα-カルボキシル基(Fig. 5)はブロックされている。(4)一方、タブトキシニンのa-アミノ基は自由である。(5)最後に、タブトキシニンのo-カルボキシル基とE-アミノ基は共にブロックされている。
タブトキシニン部分のE-プロトンの結合定数が6-7Hzと異常に低いことは、歪んだ環Zz .z3 が存在することの良い証拠で、これは必然的に13-ラクタムであるに違いない。このことは、Fig. 1に示した構造を直接的に導き出すことになる。この要約には含まれていないが、前の章で報告されたデータは、この推論をさらに後押しするものである。
2つの異なる毒素?
私が提示したデータと議論は、図1の式が野火病の毒素の正しい構造であることを説得力を持って示しています。この式はWoolleyが提案した式(図3)とは著しく異なり、乳酸を含んでいるがスレオニンを含んでいない。彼のタブトキシニンの式も私のものとは異なっている。これらの食い違いの大きさから、Woolleyらはここで説明したものとは異なる毒素を単離したのだと思われる。
この仮説にはいくつかの反論があり、どれも決定的なものではないが、それらを総合すると説得力のある図式ができあがる。私の毒素は、もともとBraunによって分離されたPseudomonas tabaciの株から調製されたものである。葉のバイオアッセイの精度の範囲内で、培養ろ液の生物活性はすべて化学的に測定された野火の毒素の量で説明することができる。野火の毒素のRF値はWoolleyが報告した値に近かった。Whatman No.1濾紙上のn-プロパノール-水(2:I)昇降式では、wildfire toxinのRFは0.30であった;Woolleyはこの系のRFを0.26と報告している。下降性フェノールを水で飽和させた系では,私は0.50のRFを得たが,Woolleyは0.57のRFを報告している。毒素の調製が不安定であったために,Woolleyは比較の基礎となるような他の物理的特性を記録することができなかったので,毒素の加水分解生成物に頼らざるを得なかったのである。
Woolleyのタブトキシニンの本物のサンプルは、D. W. Woolley夫人から提供された。私はこの物質と、私がイソタブトキシンの加水分解物から単離したタブトキシニンとを比較した。この2つのアミノ酸は、いくつかの異なる溶媒系でのクロマトグラフィーと緩衝過ヨウ素酸塩との反応において同じ挙動を示した。それらの赤外線スペクトルは2.5 Ilmから17 Ilmまで記録され、全範囲で事実上重ね合わせ可能であった。
私はまた、16年前にWoolleyが調製した毒素加水分解物を、自動アミノ酸分析装置でクロマトグラフィーにかけた。タブトキシニン1.0mol、スレオニン0.43mol、アラニン0.08mol、グリシン0.06molであった。これらのデータから、ウーリーの毒素は様々な化合物の混合物であり、その主要成分は私が特徴付けた毒素であることが示唆された。Woolleyが調製品で示した乳酸は、おそらく不純物であったと思われる。不安定な荷電化合物を扱うための効率的なイオン交換技術は開発されていなかったので、ウーリーが毒素の精製に苦労したのも無理からぬことであった。
毒素はどのように作用するのか?
今回発表された野火の毒素の構造証明は、様々な偽陽菌の種から得られる多くの関連または同一の毒素の特徴を容易に明らかにすることを可能にするものである。これらの毒素の構造は、これらの種間の関係を決定するのに有用である。
野火の毒素の新しい構造は、その作用機序についての推測を促すものである。13-ラクタム基は、自然界ではペニシリン系、セファロスポリンC系、パキスターミン系の3種類しか見つかっていない24。野火の毒素に見られる異常に反応性の高い13-ラクタム基は、その毒性作用に不可欠である可能性が高い。ペニシリンの作用機序と類似していることから25、野火の毒素は酵素の活性部位をアシル化することで何らかの酵素を阻害し、生物学的効果を発揮することが示唆された。
SindenとDurbinは、野火の毒素がグルタミン合成酵素を阻害する証拠を示した14。メチオニン・スルホキシミンは、生物学的には野火止用毒素13とほとんど同じで、グルタミン合成酵素との相互作用の間にリン酸化されるグルタミン合成酵素阻害剤である26。このことから、野火の毒素も同様に、阻害の際にリン酸化されることが示唆された(図6)。現在では、この疑問について調査することが可能になっているはずである。
20年間、野火病の毒素に関する研究は、構造不明の不純物を使って進められてきた。これらの問題の解決は、この毒素の作用機序に対する合理的な攻撃を可能にする。
R. Durbin博士、D. W. Woolley夫人、J. M. Stewart博士、A. Braun博士には試料と助言をいただいた。また、多くの友人や先生方からアドバイスや技術的な援助をいただいたことに感謝する。この研究の一部は、私がロックフェラー大学の大学院生であったときに行われたものである。
注釈
参考文献
1) Wolf, F. A.; Foster, A. C., Science, 1917, 46, 361.
2) Wolf, F. A., North Carolina Exp. Sta. Bull., 1922, 246, 1.
3) Johnson, J., and Murwin, H. F., Wisconsin Agric. Exp. Sin. Bull., 1925, 62, 1.
4) Woolley, D. W., Pringle, R. B., and Braun, A. C. J. Bioi. Chem., 1952, 197,409.
5) Woolley, D. W., Schaffner, G.,and Braun, A. c., J. Bioi. Chem., 1955, 215,485.
6) Woolley, D. W., in Plant Pathology, Problems and Progress (edit. by Holton, C. S., Fischer, G. W., Fulton, R. W., Hart, H., and McCallan, S. E. A.), 130 (University of Wisconsin Press Madison, 1959).
7) Stewart, J. M., J. Amer. Chem. Soc., 1961, 83, 435.
8) Sinden, S. L., and Durbin, R. D., Phytopathology, 1970, 60, 360.
9) Lovrekovich, L., and Farkas, G. L., Nature, 1963, 198, 710.
10) Lovrekovich, L., Klement, Z., and Farkas, G. L., Nature, 1963, 197, 917.
11) Braun, A. C., Phytopath., 1955, 45, 659.
12) Sinden, S. L., Durbin, R. D., Uchytil, T. F., and Lamar, jun., c., Toxicol. Appl. Pharmacol., 1969, 14, 82.
13) Braun, A. C., Proc. US Nat. Acad. Sci., 1950, 36, 423.
14) Sinden, S. L., and Durbin, R. D., Nature, 1968, 219, 379.
15) Lamar, jun., c., Sinden, S. L., and Durbin, R. D., Biochem. Pharmacol., 1969, 18, 521.
16) Owens, L. D., Science, 1969, 165, 18.
17) Spackman, D. H., Stein, W. H., and Moore, S., Anal. Chem., 1958, 30, 1190.
18) Sheinblatt, M., J. Amer. Chem. Soc., 1966, 88, 2845.
19) Woolley, D. W., Schaffner, G., and Braun, A. C., J. Bioi. Chern., 1952, 198, 807.
20) Akabori, S., Ohno, K., and Narita, K., Bull. Chern. Soc. Jap., 1952, 25, 214.
21) Turner, R. A., and Schmerzler, G., J. Amer. Chern. Soc., 1954, 76, 949.
22) Barrow, K. D., and Spotswood, T. M., Tetrahedron Lett., 1965, 3325.
23) Bothner-By, A. A., in Advances in Magnetic Resonance (edit. by Waugh, J. S.), I, 195 (Academic Press, New York, 1965).
24) Kikuchi, T., and Uyeo, S., Chern. Pharm. Bull., 1967, 15, 549.
2S) Rogers, H. J., and Perkins, H. R., Cell Walls and Membranes (Spon, London, 1968).
26) Rowe, W. B., Ronzio, R. A., and Meister, A., Biochemistry, 1969, 8, 2674.