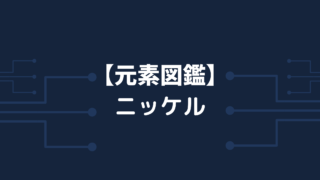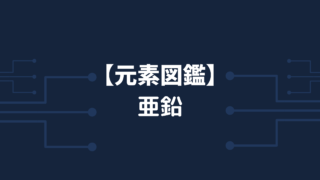銅に関する情報をまとめました。
銅の基本情報
| 和名 | 銅 |
|---|---|
| 英名 | Copper |
| 語源 | 地中海キプロス島 (Cyprus) |
| 元素記号 | Cu |
| 原子番号 | 29 |
| 原子量 | 63.55 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 赤色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 8.960 g/cm3(20℃) |
| 融点 | 1084.5℃ |
| 沸点 | 2562℃ |
| 発見者 | 古来 |
| 含有鉱物 | 自然銅, 黄銅鉱 |
銅の主な特徴
- 遷移金属元素で、周期表第11族に属す
- 赤褐色の金属光沢をもち、高い電気伝導性・熱伝導性で知られている(銀に次ぐ2位)
- 延性・展性にも優れ、加工性が高いことから、古くから金属器や電線、合金の材料として広く使われてきた
- 酸化数は +1(Cu⁺)と +2(Cu²⁺)があり、色彩豊かな化合物を形成する
銅の歴史
発見
銅は人類が最も早く利用した金属のひとつで、紀元前9000年頃には中東で加工されていました。
紀元前4000年には銅とスズを混ぜた青銅(ブロンズ)が誕生し、「青銅器時代」が始まりました。
名前の由来
元素記号「Cu」は、ラテン語の “cuprum” に由来し、これは「キプロス島の金属」を意味します。
古代においてキプロス島は重要な銅の産地であり、その名が定着しました。
銅の主な用途
銅は導電性と加工性を活かして、多くの分野で利用されています:
- 電気・電子材料: 電線・ケーブル・基板配線・モーターコイル
- 建材・配管: 耐腐食性と加工性を生かした給排水管、屋根材
- 合金: 青銅(Cu-Sn)、黄銅(Cu-Zn)、洋白(Cu-Ni-Zn)など
- 触媒: メタノール合成、CO酸化、水素化などの反応触媒
- 硬貨: 各国の通貨の材料として広く使用(日本の10円玉も銅合金)
銅の生成方法
銅は主に硫化鉱(黄銅鉱CuFeS₂)や酸化鉱から以下の工程で製錬されます:
- 乾式製錬: 鉱石を焼成して硫黄を除き、転炉で銅を濃縮(粗銅)
- 電解精錬: 粗銅を電気分解し、99.99%以上の高純度電解銅を得る
- 湿式製錬: 酸性浸出液から銅イオンを溶出し、電解採取
銅を含む化合物
銅は豊富な化合物を形成し、特有の色彩を示します:
- CuSO₄·5H₂O(硫酸銅(II)五水和物): 鮮やかな青色結晶。試薬・農薬・めっき液に使用
- CuCl(塩化銅(I)): 白色結晶。光や酸素で変色
- CuO(酸化銅(II)): 黒色粉末。セラミックや触媒に利用
- Cu₂O(酸化銅(I)): 赤色固体。半導体材料にも応用
- 銅錯体: アンモニア・エチレンジアミンとの錯形成により多彩な構造と色を持つ
銅に関する研究事例
銅は無機化学、エネルギー材料、生体無機化学など多岐にわたる研究対象です:
- 酸素還元反応触媒: 燃料電池やCO₂還元電極への応用
- 半導体材料: Cu₂OやCuSCNなどの新規光電変換材料
- 生体内酵素: シトクロムcオキシダーゼ、スーパーオキシドジスムターゼなどの活性中心
- 銅触媒の有機反応: Ullmann反応、Azide-Alkyne Cycloaddition(CuAAC)など
- 抗菌性銅材料: 銅ナノ粒子の抗菌作用を利用した医療用コーティング
筆者の薦める1冊
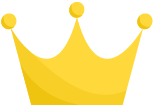 第1位 元素検定2
第1位 元素検定2元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
リンク
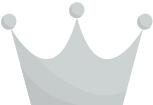 第2位 世界で一番美しい元素図鑑
第2位 世界で一番美しい元素図鑑この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
リンク