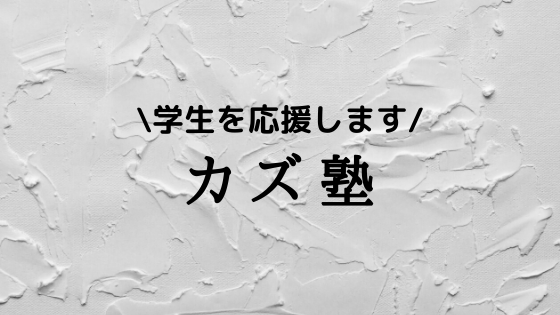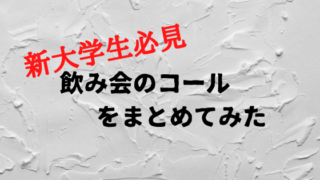理想溶液においては、いかなる条件下においても理想的な振舞いをする。
しかしながら、実在溶液では理想的な振舞いからのずれが生じる。
前記事では、気体の不完全性を考慮するために、フガシティーという量を導入した。
ここでは、実在溶液を扱うために、活量 (activity) という概念を導入する。
それにより、理想溶液の取扱いで登場した式の形をほとんど変えないまま、実在溶液に適用できるようになる。
A:溶媒
B:溶質
J:一般の組成
溶媒の活量
溶媒の化学ポテンシャルは、実在か理想かに関わらず、
\[
μ_A = {μ_A}^* + RT\ln{\frac{p_A}{{p_A}^*}}
\]
を少し変形した式で与えられる。ここで、\({p_A}^*\)は純粋なAの蒸気圧、\(p_A\)は溶液中の組成の一つとして存在するときの蒸気圧を表す。
理想溶液中の溶媒は、すべての濃度でラウールの法則 (\(p_A = x_A {p_A}^*\)) に従うから、上記の式は以下のように書き換えられる。
\[
μ_A = {μ_A}^* + RT\ln{x_A}
\]
溶液がラウールの法則に従わない場合は、以下のように表される。
\[
μ_A = {μ_A}^* + RT\ln{a_A} \tag{1}
\]
したがって、式の形は保持することができる。
ここで登場した物理量 \(a\) が活量であり、\(a_A\) は A の活量を表す。これは一種の実効モル分率である。
(1)式は実在溶液と理想溶液のどちらにも有効なので、この式を \(μ_A = {μ_A}^* + RT\ln{(p_A / {p_A}^*})\) と比較すると、
\[
a_A = \frac{p_A}{{p_A}^*} \tag{2}
\]
となることがわかる。したがって、蒸気圧を実験により測定することができれば、(2)式より活量を求めることができる。
また、溶質の濃度が0に近づくにつれて、溶媒はラウールの法則に次第と従うようになる。そのため、溶媒の活量は \(x_A → 1\) につれて、モル分率に近づく。
\[
x_A → 1 のとき, a_A → x_A
\]
このようになることは、活量係数 (activity ecofficient) γ(ガンマ)を導入することで、表すことができる。
\[
a_A = γ_A x_A x_A → 1 につれて, γ_A → 1
\]
このとき、溶媒の化学ポテンシャルは、
\[
μ_A = {μ_A}^* + RT\ln{x_A} + RT\ln{\gamma_A}
\]
となる。
溶質の活量
溶質について活量係数と標準状態を定義するとき、\(x_B → 0\) で理想希薄溶液の振舞いに近づくことが問題となる。
理想希薄溶液
ヘンリーの法則を満たす溶質Bは、\(p_B = K_B x_B\) で与えられる蒸気圧をもつ。ここで、\(K_B\) は実験により求められる定数である。
このとき、Bの化学ポテンシャルは、
\[
μ_B = {μ_B}^* + RT\ln{\frac{p_B}{{p_B}^*}} = {μ_B}^* + RT\ln{\frac{K_B}{{p_B}^*}} + RT\ln{x_B}
\]
と表される。\(K_B\) と \({p_B}^*\) は溶質に特有のものであるため、第1項と第2項をまとめると、新しい化学ポテンシャル \({\mu_B}^\circ\) は、
\[
{\mu_B}^\circ = {\mu_B}^* + RT\ln{\frac{K_B}{{p_B}^*}} \tag{3}
\]
と表される。これより、理想希薄溶液における溶質の化学ポテンシャルはそのモル分率によって、
\[
\mu_B = {\mu_B}^\circ + RT\ln{x_B} \tag{4}
\]
と表される。したがって、溶液が理想的であれば、\(K_B = {p_B}^*\) であることから、(3)式は \({\mu_B}^\circ = {\mu_B}^*\) となることがわかる。
実在溶液
更新をお待ちください
活量の質量モル濃度による表現
更新をお待ちください
正則溶液の活量
更新をお待ちください