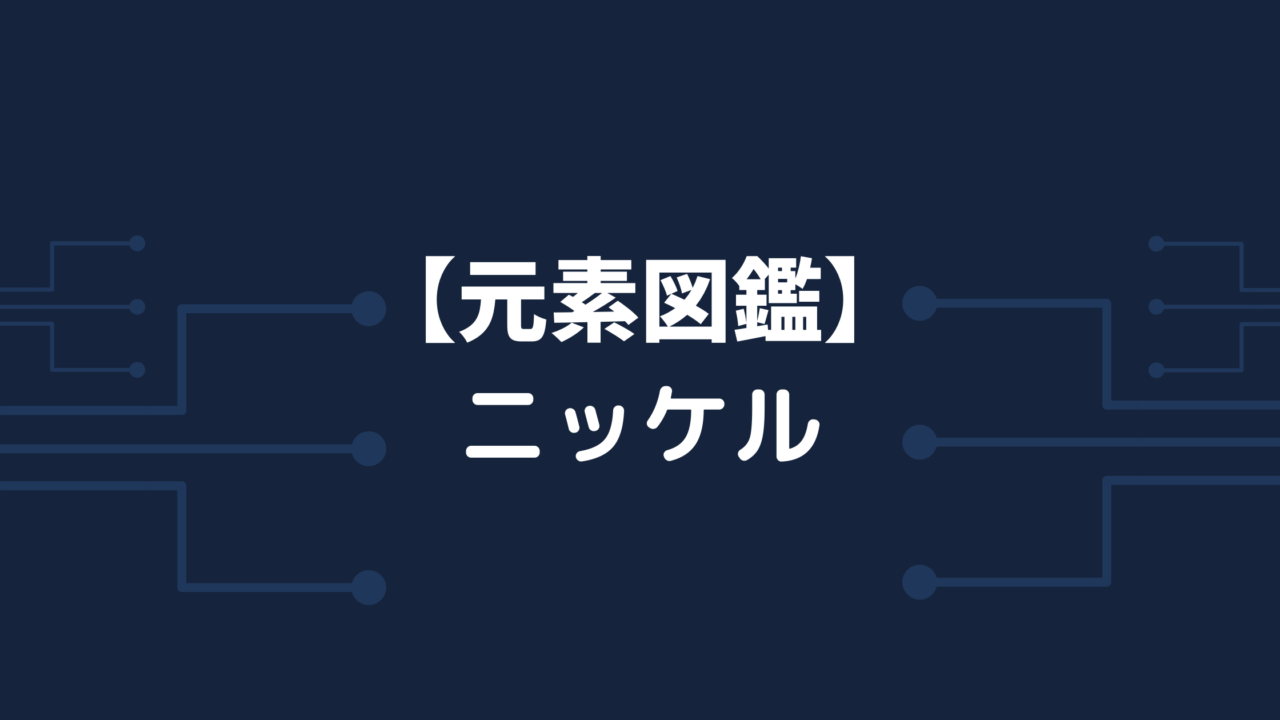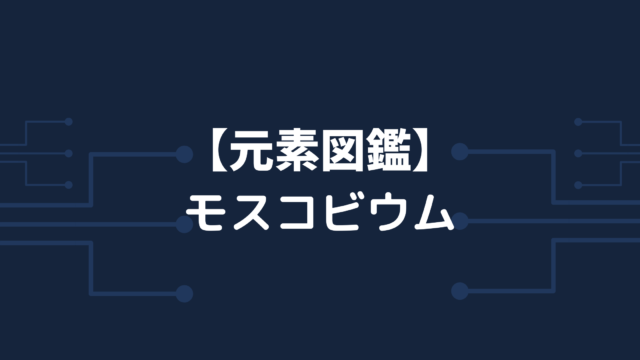ニッケルに関する情報をまとめました。
ニッケルの基本情報
| 和名 | ニッケル |
|---|---|
| 英名 | Nickel |
| 語源 | ドイツ語「悪魔の銅(Kupfernickel)」 |
| 元素記号 | Ni |
| 原子番号 | 28 |
| 原子量 | 58.69 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 灰白色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 8.902 g/cm3(25℃) |
| 融点 | 1455℃ |
| 沸点 | 2913℃ |
| 発見者 | クローンステット(スウェーデン)[1751年] |
| 含有鉱物 | 紅砒ニッケル鉱 |
ニッケルの主な特徴
- 遷移金属元素で、周期表第10族に属す
- 銀白色で光沢があり、空気中では比較的安定な金属であり、耐食性と延性に優れている
- 常磁性を示し、合金材料・電池・触媒・錯体化学において不可欠な金属
- 微量ながら生体必須元素としても知られている
リチウムの歴史
発見
ニッケルは1751年、スウェーデンの鉱山技師・化学者アクセル・フレドリク・クローナステットによって、鉱石ニッケル鉱(ニコリット)から発見・単離されました。
当初は銅を含む鉱石と誤認されていたため、銅の代用品としての研究が進められました。
名前の由来
「ニッケル(Nickel)」の語源は、ドイツ語の“kupfernickel(悪魔の銅)”に由来します。
この名は「銅を含むと思っていた鉱石から銅が取れなかった」ことへの皮肉に基づいています。
ニッケルの主な用途
ニッケルはその物理的・化学的性質を活かし、さまざまな分野で利用されています:
- 合金材料: ステンレス鋼(Fe-Cr-Ni)、ニクロム線(Ni-Cr)などの耐食・耐熱合金
- 電池: ニッケル水素電池(NiMH)、ニッケルカドミウム電池(NiCd)の正極材
- めっき: 電気ニッケルめっきや無電解めっきによる装飾・耐食保護
- 触媒: 水素化反応(ラネーニッケル)や自動車排ガス浄化触媒
- 化学工業: アクリロニトリルや脂肪酸の合成などに利用
ニッケルの生成方法
ニッケルは主に硫化鉱(ペントランド鉱)や酸化鉱から以下の工程で抽出されます:
- 乾式製錬: 焼成 → 還元 → 精錬の工程で金属ニッケルを得る
- 湿式製錬: 鉱石を酸・アンモニアなどで溶解し、選択的にニッケルを抽出・電解精製
- カーボニル法: ニッケルと一酸化炭素の反応で揮発性Ni(CO)₄を形成し、熱分解により純粋なNiを得る
ニッケルを含む化合物
ニッケルは主に+2の酸化数で安定した化合物を形成し、多くは緑色〜青色の色を示します:
- NiCl₂(塩化ニッケル(II)): 緑色結晶。錯体合成や電気めっきに使用
- NiSO₄(硫酸ニッケル): 青緑色塩。ニッケルめっきや乾電池の電解液
- ニッケル錯体: 八面体型錯体が多く、磁性・光学特性に優れる(例:Ni(en)₃²⁺)
- ラネーニッケル: 水素化反応に使われる粉末状触媒。表面積が大きく高活性
- Ni(CO)₄(ニッケルカルボニル): 揮発性で高毒性。精製工程に利用されるが注意が必要
ニッケルに関わる研究事例
ニッケルは材料科学・触媒化学・環境科学・生体無機化学などの分野で活発に研究されています:
- リチウムイオン電池の高容量化: Ni-rich正極材料(NCA、NCM)の研究が進行中
- ニッケル錯体触媒: クロスカップリング、炭素-ヘテロ原子結合形成への応用
- ラネーニッケルの改良: 反応選択性・耐久性向上に向けた表面修飾研究
- 生体内のニッケル酵素: ニッケラーゼ(ureaseなど)の活性機構やモデル錯体の設計
- ニッケル汚染除去: 水質中のNi²⁺イオンを吸着・沈殿・キレートで除去する研究
参考図書
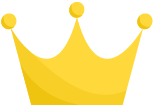 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
リンク
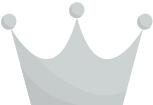 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
リンク
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。
リンク