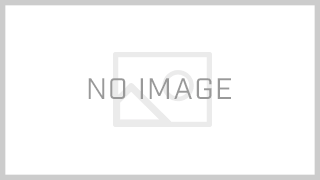チオール官能基(–SH)の構造・性質・酸化・反応・生体機能まで徹底解説
チオール(thiol)は、–SH基を持つ有機硫黄化合物であり、アルコール(–OH)に類似した構造ながら、反応性や物理的性質に大きな違いがあります。
特に強烈なにおい、酸化されやすさ、金属との高い親和性が特徴です。
生体内ではアミノ酸の1種「システイン」に含まれ、タンパク質の構造保持(ジスルフィド結合)や酸化還元バランスの維持に重要な役割を果たします。
Contents
チオールの構造と命名法
チオールは、炭素にスルフヒドリル基(–SH)が結合した構造を持ち、一般式は R–SH で表されます。
酸素(O)を硫黄(S)に置き換えたアルコールのアナログと考えると理解しやすいです。
IUPAC命名法
- 炭素骨格のアルカン名に「thiol(チオール)」を付ける
- 必要に応じて番号を付加する(–SHが主官能基)
命名例
- CH₃SH → メタンチオール(methanethiol)
- CH₃CH₂SH → エタンチオール(ethanethiol)
- PhSH → ベンゼンチオール(thiophenol)
慣用名も広く使われており、チオール類は「マーカプタン」とも呼ばれます(例:エチルメルカプタン)。
チオールの物理的性質
- 強烈かつ不快なにおい(天然ガスに添加される)
- 沸点・融点は対応するアルコールよりも低い
- 水素結合を形成しにくいため、水溶性は低い
- 空気中で容易に酸化されやすい(自動酸化)
チオールの酸性
–SHは比較的弱い酸性を持ちますが、アルコールよりも酸性が強い(pKa ≈ 10–11)。
そのため、塩基の存在下で容易にチオラートアニオン(RS⁻)を形成し、求核剤として作用します。
R–SH ⇌ R–S⁻ + H⁺チオラートアニオンは、親電子性の中心(エポキシド、ハロアルカンなど)に反応しやすく、置換反応の中間体として活躍します。
チオールの主な反応
① 酸化反応
チオールは容易に酸化され、ジスルフィド結合(–S–S–)を形成します。
2 R–SH + [O] → R–S–S–R + H₂O- 酸化剤:O₂(空気中でも起こる)、H₂O₂、I₂ など
- 生体内ではシステイン同士の反応によりタンパク質の三次構造を安定化
② 求核置換反応
R–S⁻ + R'–X → R–S–R' + X⁻チオラートアニオンはSN2反応でハロアルカンと反応し、スルフィド(エーテルのS版)を形成します。
③ 金属との錯形成
- 金、銀、銅などの軟金属イオンと強い錯体を形成
- ナノ粒子修飾、金属表面保護、センサー材料として応用
④ 脱水縮合
- チオール + アルコール → チオエーテル(酸/塩基条件)
- アミンとの反応でチオアミドへ
生体内でのチオールの役割
① システイン(アミノ酸)
- タンパク質中の唯一の–SH含有アミノ酸
- 酸化によりジスルフィド結合(S–S)を形成 → 立体構造維持
② グルタチオン(GSH)
- 細胞内の主要な還元性物質
- 酸化ストレスから細胞を守る
③ 補酵素機能
- チオール基が金属を捕捉したり、電子授受反応に関与
チオールの応用と実用例
① 天然ガスの検知
- 無臭の天然ガスに、エタンチオールなどを微量添加
- 漏れ検知のための「におい付け」
② 分析化学
- 金属イオンと結合して発色 → 定量測定に使用
③ 表面修飾とナノ材料
- 金ナノ粒子へのチオール固定化(SAM:自己組織化単分子膜)
- 生体適合性材料・センサーの設計
④ 医薬・創薬
- 還元性の高い薬剤(抗酸化物質)として作用
- チオール含有薬(N-アセチルシステインなど)
チオールの取扱いと注意点
- 空気中で酸化されやすく、保存には脱酸素・冷暗所保管が望ましい
- 刺激臭が強く、換気の良い環境で取り扱う
- 酸化物やジスルフィドとの平衡に注意
まとめ:チオールは小さな–SHに秘められた高反応性・生体機能性官能基
- チオール(–SH)はアルコールに類似した構造を持つが、反応性ははるかに高い
- 酸化 → ジスルフィド、還元、求核反応、金属錯形成などが主要反応
- 生体内ではシステインやグルタチオンにより重要な生理機能を担う
- 工業・分析・創薬・材料分野で活用が進む
次回は、「エーテル(R–O–R’)」をテーマに、その構造、反応性、酸性度との比較、合成法、応用について詳しく解説していきます。
🧭 関連リンク
- 👉 【まとめ記事】官能基シリーズ 一覧はこちら
- 👉 【第8回】スルホン酸官能基
- 👉 【第10回】エーテル官能基(近日公開)