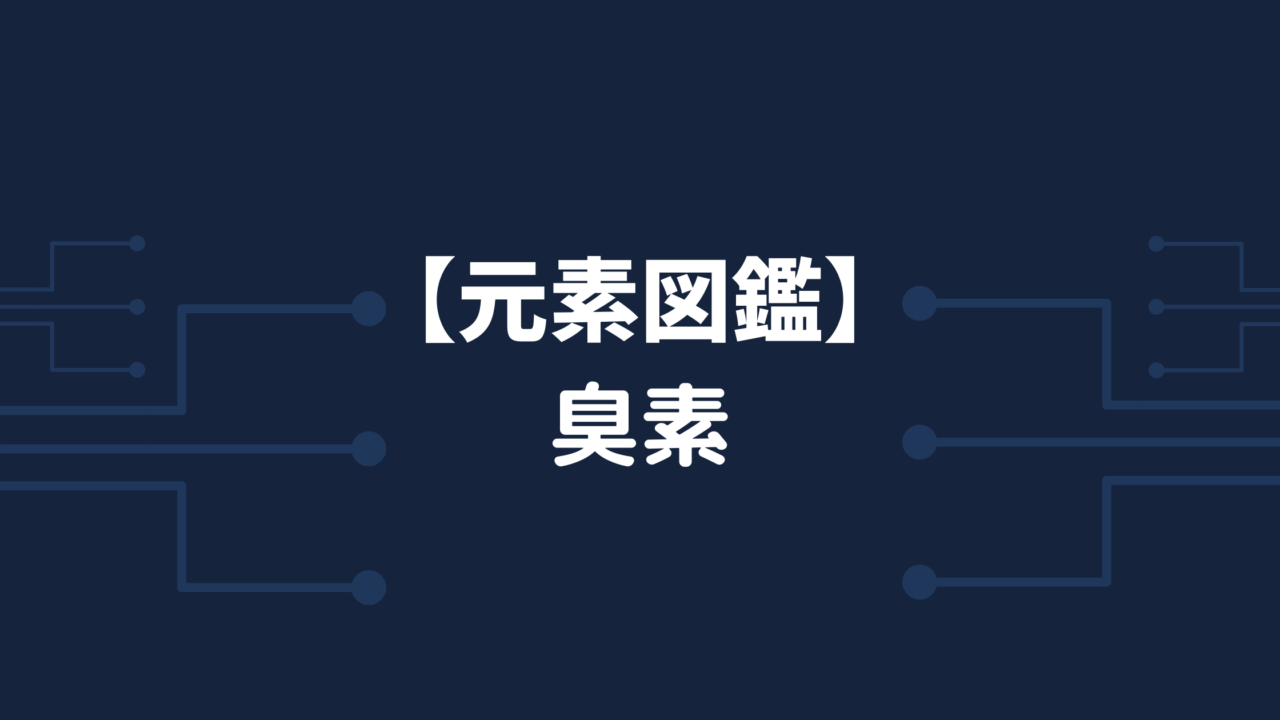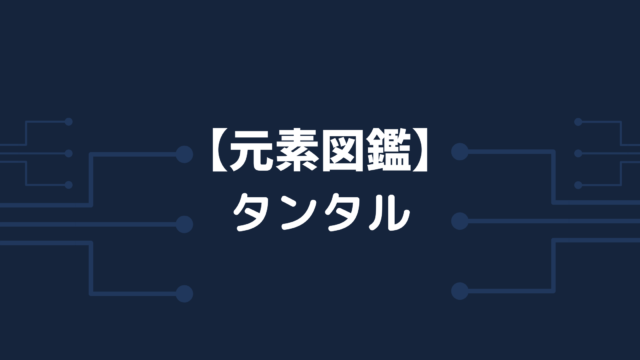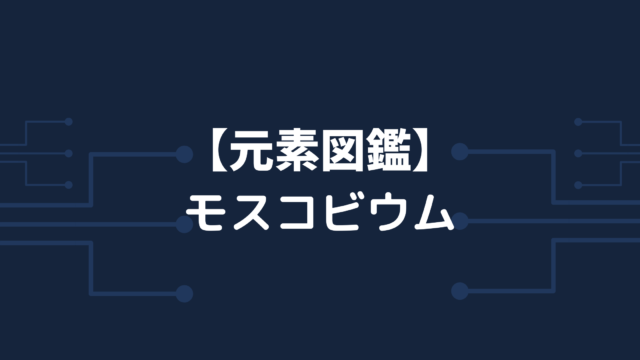臭素は、原子番号35、原子量79.9の元素であり、ハロゲン元素の一つです。
単体(Br2)は常温常圧で刺激臭のある赤褐色の液体である。
反応性は塩素より弱く、猛毒である。
海水中に微量存在する。
臭素の基本情報
| 和名 | 臭素 |
|---|---|
| 英名 | Bromine |
| 語源 | ギリシャ語「刺激臭・悪臭(bromos)」 |
| 元素記号 | Br |
| 原子番号 | 35 |
| 原子量 | 79.90 |
| 常温(25℃)での状態 | 液体 |
| 色 | 赤褐色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 3.120 g/cm3(液体, 20℃) |
| 融点 | -7.2℃ |
| 沸点 | 58.8℃ |
| 発見者 | レービヒ(ドイツ), バラール(フランス)[1817年] |
| 含有鉱物 | 含臭素角銀鉱 |
臭素の主な特徴
- ハロゲン元素で、周期表第17族に属す
- 常温常圧で赤褐色の液体として存在する数少ない元素のひとつであり、強い刺激臭を放つ
- 毒性・腐食性が高く、皮膚や粘膜に対して有害ですが、化学反応性の高さから工業用途で重要
- 有機臭素化合物としては、難燃剤、医薬品、農薬、写真フィルムなど広範な用途がある
臭素の歴史
発見
臭素は1826年、フランスの化学者アントワーヌ・バラールによって発見されました。
彼は海藻から抽出された塩類から新しい赤褐色の液体を得て、これを新元素と同定しました。
名前の由来
臭素の語源は、ギリシア語の「bromos(悪臭)」に由来します。
これは、特有の強く不快な臭いにちなんだ命名です。
臭素の主な用途
臭素およびその化合物は、以下のような幅広い用途を持ちます:
- 難燃剤: 臭素化有機化合物(ポリ臭化ビフェニルなど)はプラスチックや繊維の防炎処理に使用
- 写真材料: 臭化銀(AgBr)は感光材料としてフィルムや印画紙に利用
- 有機合成: 臭素化反応(Br₂)やNBS(N-ブロモスクシンイミド)を用いたラジカル反応
- 消火剤: ハロン系化合物はかつて航空機・電子機器用の消火剤に使用(現在は使用制限あり)
- 農薬・医薬品: 殺菌剤・除草剤・鎮静剤・抗けいれん薬の中間体に使用
臭素の生成方法
臭素は主に海水や地下塩水に含まれる臭化物イオン(Br⁻)から次のようにして製造されます:
- 酸化分離: 塩素ガスを用いてBr⁻を酸化し、分子状臭素(Br₂)を遊離させる
- 抽出・精製: 得られたBr₂を有機溶媒や蒸留により回収・精製
- 副産物回収: 一部はブロム化プロセスや鉱工業排液から副生される
臭素を含む化合物
臭素は主に−1と+1、+3、+5の酸化数をとる化合物を形成します:
- HBr(臭化水素): 無色気体。水に溶けて強酸(臭化水素酸)となる
- AgBr(臭化銀): 光に対して感光性をもつ。写真フィルムに利用
- Br₂(臭素): 分子状態で強い酸化剤。有機臭素化に使用
- NaBr(臭化ナトリウム): 医薬品や写真現像液、分析試薬として使用
- 有機臭素化合物: ブロモベンゼン、ブロモエタン、ポリ臭化化合物など多岐にわたる
臭素に関わる研究事例
臭素に関する研究は、材料化学、分析化学、環境科学などの分野で進められています:
- 光学材料研究: AgBr薄膜の光感応特性の改良やナノ構造化
- 触媒化学: 臭素を含む有機触媒の開発と反応機構解析
- 大気化学: 臭素化合物によるオゾン層破壊メカニズムの解明
- 臭素のバイオロジー: 神経伝達に関連する臭化ナトリウムの作用や安全性評価
- 廃棄臭素化合物の処理: 難燃剤由来の臭素化有機物の分解技術(熱分解・光分解など)
参考図書
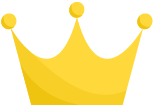 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
リンク
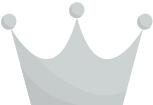 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
リンク
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。
リンク