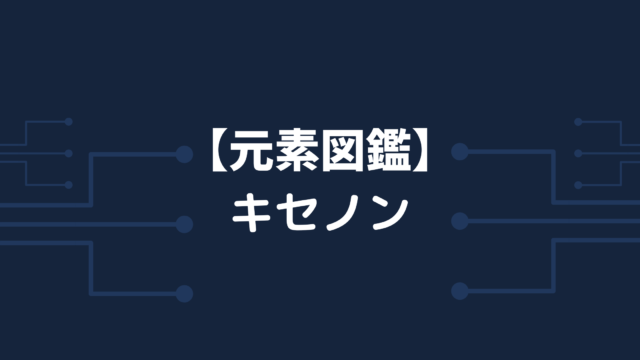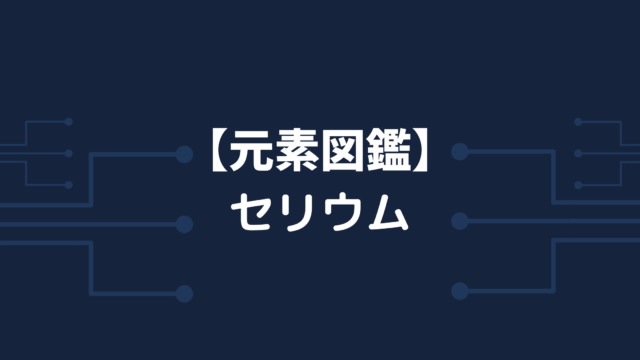【元素図鑑】マンガン Mn【電池で大活躍】
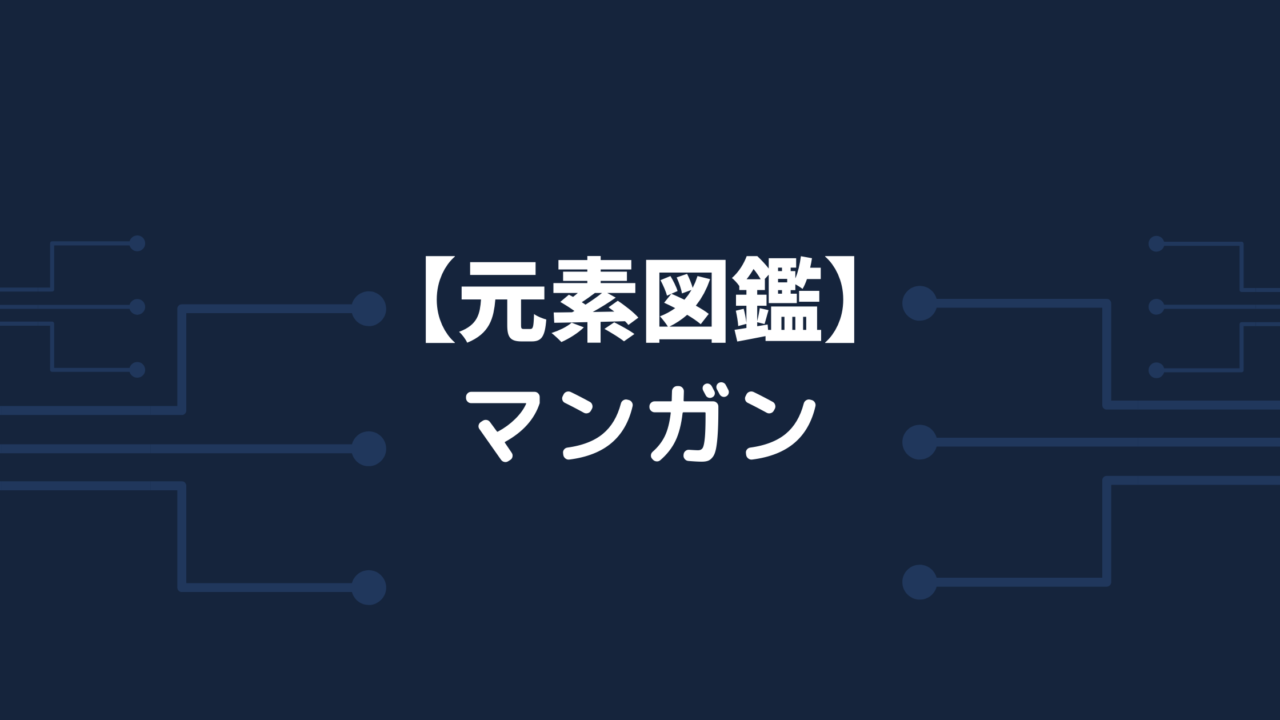
マンガンに関する情報をまとめました。
マンガンの基本情報
| 和名 | マンガン |
|---|---|
| 英名 | Manganese |
| 語源 | 鉱石マンガナス (Manganase) |
| 元素記号 | Mn |
| 原子番号 | 25 |
| 原子量 | 54.94 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 銀白色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 7.440 g/cm3(20℃) |
| 融点 | 1246℃ |
| 沸点 | 2062℃ |
| 発見者 | ガーン(スウェーデン)[1774年] |
| 含有鉱物 | 軟マンガン鉱 |
マンガンの主な特徴
- 遷移金属元素で、周期表第7族に属す
- 硬くもろい銀灰色の金属で、単体は空気中で酸化されやすく安定ではない
- +2 から +7 までの広い酸化状態をとり、それぞれ異なる色や反応性を示す
- 化学的多様性に加え、合金・乾電池・触媒・生体内酵素の成分としても広く利用されている
リチウムの歴史
発見
マンガンの酸化物は古代から顔料(褐色石など)として用いられていました。
金属としては、1774年にスウェーデンの化学者ヨハン・ゴットリーブ・ガーンが酸化マンガンを炭で還元することにより単離しました。
名前の由来
「マンガン(Manganese)」という名前は、マグネタイトと混同されていた鉱石「マグネシア(Magnesia)」に由来し、
ラテン語の “manganēsia” から派生しました。
マンガンの主な用途
マンガンは多くの産業分野で不可欠な金属です:
- 製鋼・合金: 鉄の脱酸・脱硫に使用され、耐摩耗性の高いマンガン鋼も製造
- 乾電池: 二酸化マンガン(MnO₂)はアルカリ電池やマンガン電池の正極材料
- 顔料: 紫、茶、黒色系の陶磁器・ガラス着色剤として利用
- 化学触媒: 酸化還元反応や水分解反応における電子供与体
- 生体内酵素: スーパーオキシドジスムターゼ(Mn-SOD)など、抗酸化作用に寄与
マンガンの生成方法
マンガンは主に鉱石パイロルス石(MnO₂)から以下の方法で精製されます:
- 炭素還元法: 高温で酸化マンガンをコークスとともに加熱し金属Mnを得る
- 電解法: 高純度の電解マンガン金属(EMM)を得る方法。主に中国で生産
- 化学精製: 各種マンガン塩として工業原料に加工
マンガンを含む化合物
マンガンは多様な酸化数と色彩を持つ化合物を形成します:
- MnO₂(二酸化マンガン): 黒色固体。電池や酸化剤に使用
- KMnO₄(過マンガン酸カリウム): 赤紫色の強力な酸化剤。殺菌・分析に使用
- Mn²⁺: 淡いピンク色のイオン。生体内酵素で重要
- MnO₄⁻: 酸化数+7。強力な酸化剤として知られる
- MnCl₂・MnSO₄: 工業用触媒・栄養補助材料などに応用
マンガンに関わる研究事例
マンガンは無機化学・生物無機化学・エネルギー材料の分野で多くの研究対象となっています:
- マンガン酸化物の触媒研究: 燃料電池、水分解(OER)触媒としての応用
- マンガン錯体による酸素発生模倣: 光合成系IIのMn₄CaO₅クラスターの人工模倣
- マンガンレドックス反応の機構解明: 電池反応や酸化還元触媒に関与
- 生体内での役割研究: 酵素活性、神経機能への影響、必須微量元素としての栄養学研究
- 過マンガン酸の環境応用: 汚染水処理や土壌中の有機物分解
参考図書
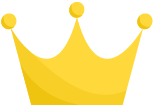 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
リンク
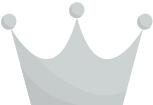 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
リンク
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。
リンク