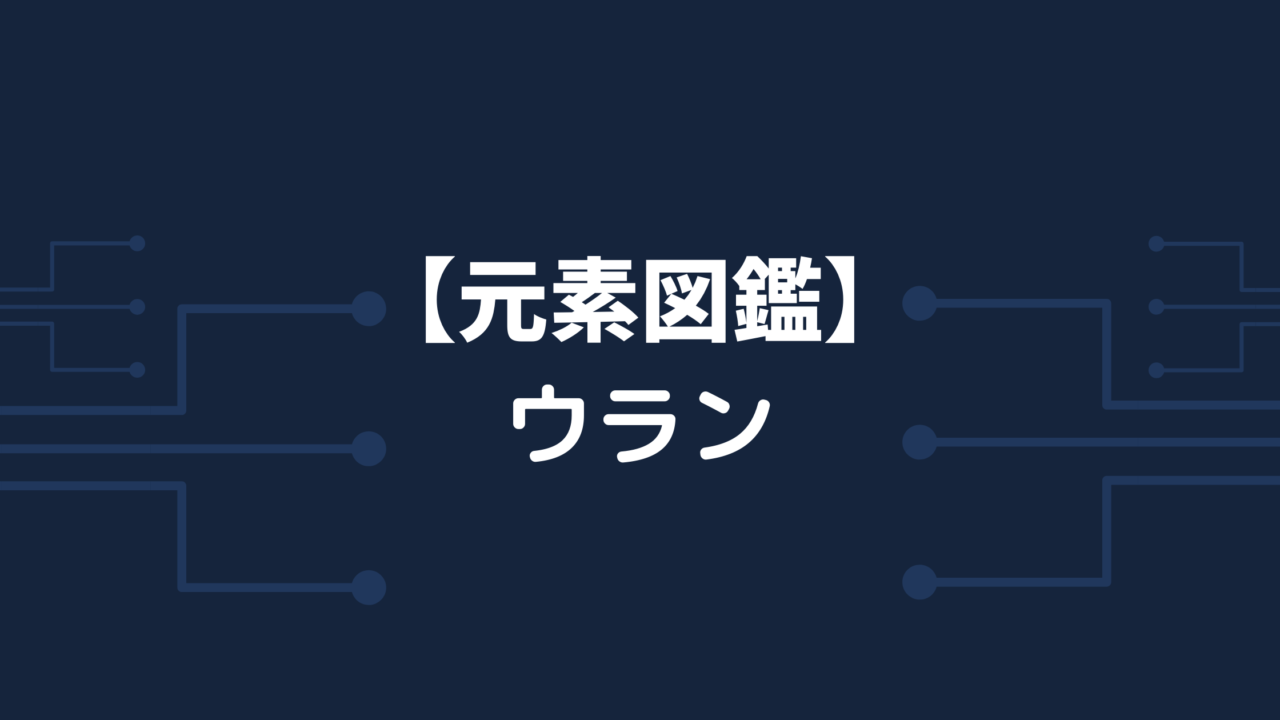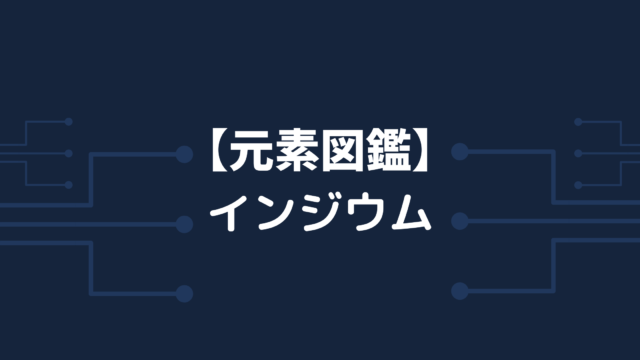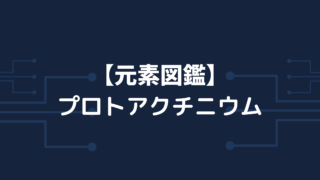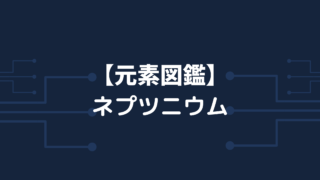ウランは、アクチノイド元素で、原子番号92の元素です。
ウランの基本情報
| 和名 | ウラン |
|---|---|
| 英名 | Uranium |
| 語源 | 天王星 (Uranus) |
| 元素記号 | U |
| 原子量 | 238.0 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 銀白色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 18.950 g/cm3(20℃) |
| 融点 | 1132.3℃ |
| 沸点 | 4172℃ |
| 発見者 | クラップロート(ドイツ)[1789年] |
| 含有鉱物 | 閃ウラン鉱, リン灰ウラン鉱 |
| 項目 | トリウム (Th) | ウラン (U) |
|---|---|---|
| 原子番号 | 90 | 92 |
| 主な天然同位体 | Th-232(ほぼ100%) | U-238(約99.3%)、U-235(約0.7%) |
| 天然存在量 | ウランの約3~4倍 | トリウムより少ない |
| 放射能 | 弱い(Th-232の半減期:約140億年) | 強い(U-238:約45億年、U-235:約7億年) |
| 核分裂性 | 自発的には分裂しない(核変換が必要) | U-235は直接核分裂性 |
| 燃料としての利用 | Th-232 → U-233に変換して使用(増殖型) | U-235はそのまま核燃料に利用可能 |
| 核兵器への利用性 | 困難(U-233は濃縮が難しく高放射線) | U-235は濃縮で核兵器利用可能 |
| 廃棄物の放射性寿命 | 比較的短命な核分裂生成物が多い | 長寿命アクチニドが多く含まれる |
| 現在の商用利用 | 研究段階(主にインド、中国など) | 広く使用(軽水炉、加圧水型炉など) |
| 安全性 | 増殖炉や溶融塩炉での高い安全性が期待される | 実績はあるが、高圧・冷却材管理が必要 |
ウランの主な特徴
- アクチニウム系列に属する金属元素で、自然界で最も重い原子
- 銀白色の金属で放射性を持ち、自然界では主にU-238(99.3%)とU-235(0.7%)の同位体として存在する
- 化学的には+6価、+5価、+4価があり、特に+6価のウラニルイオン(UO₂²⁺)がよく知られている
- 比重は18.95と非常に高く、熱中性子を吸収する性質から原子力エネルギー源として極めて重要
ウランの歴史
発見
ウランは1789年、ドイツの化学者マルティン・クラプロートによって、鉱石「ピッチブレンド(瀝青ウラン鉱)」から発見されました。
当時は酸化物(UO₂)として分離されただけで、単体金属としてのウランは1841年にフランスの化学者ペリゴによって得られました。
名前の由来
元素名「ウラン(Uranium)」は、1781年に発見された天王星(Uranus)にちなんで命名されました。
当時の天文学的発見と化学の発見が重なった象徴的な命名です。
ウランの主な用途
ウランの最大の用途は原子力発電や核兵器の燃料です。
- 原子力発電: ウラン-235が核分裂を起こすことで大量のエネルギーを発生
- 核兵器: 高濃縮ウラン(HEU)は核爆弾に使用される
- 劣化ウラン: 原子力燃料に使われた後のU-238は弾芯・遮蔽材などに使用
- ガラス・陶器: ウラン化合物は古くは黄色や緑色の着色剤に用いられた(現在は規制)
- 研究用途: 中性子源や放射性標識物質としての利用
ウランの生成方法
ウランは自然界でウラン鉱石として存在し、以下のようにして抽出・精製されます:
- 鉱石採掘: 主にピッチブレンド(UO₂)、カルノー石、ウラン雲母など
- 酸・アルカリ処理: 溶解後、溶媒抽出やイオン交換で精製
- 濃縮: 遠心分離法によりU-235の割合を高める
- 燃料加工: UO₂などに加工し、燃料ペレットとして原子炉に投入
ウランを含む化合物
ウランは多価元素で、さまざまな酸化状態を取り、以下のような代表的化合物を形成します:
- 酸化ウラン(IV)(UO₂): 黒色粉末、軽水炉などの燃料
- 酸化ウラン(VI)(UO₃): 黄褐色粉末、可溶性が高い
- ウラニルイオン(UO₂²⁺): 水溶液中で安定、ウランの移動に関与
- 六フッ化ウラン(UF₆): 気体遠心分離による濃縮に用いられる
- 硝酸ウラニル(UO₂(NO₃)₂): 再処理工程で生成される中間体
ウランに関わる研究事例
ウランに関する研究はエネルギー、安全保障、環境保全の分野で進められています:
- 高速増殖炉の燃料: U-Puサイクルによる燃料再利用
- 濃縮・再処理技術の最適化: 遠心分離、レーザー分離など
- ウラン汚染水の浄化: ゼオライト・活性炭・錯体吸着剤の開発
- 核兵器不拡散研究: 使用済み燃料のトレーサビリティ確保
- 自然界における移動性評価: 土壌中のウランの溶出挙動や拡散モデル
筆者の薦める1冊
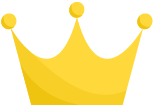 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
リンク
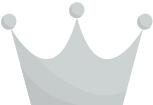 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
リンク
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。
リンク