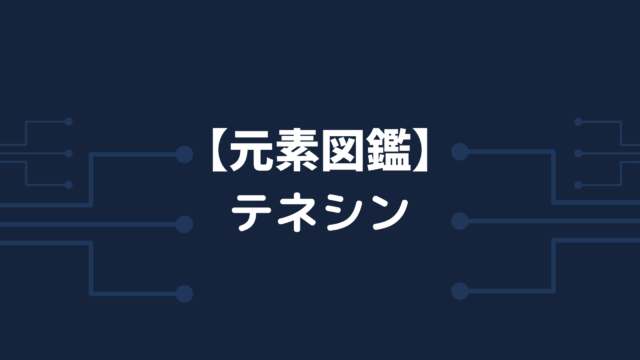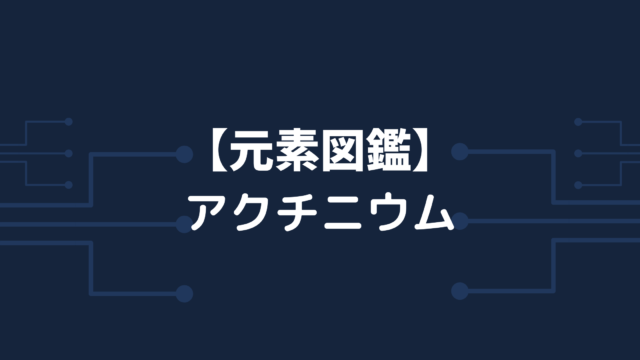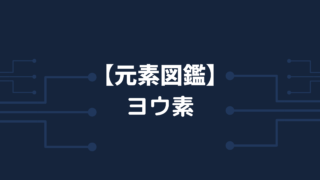【元素図鑑】テルル Te【携帯ショップの方が知名度が高い?!】
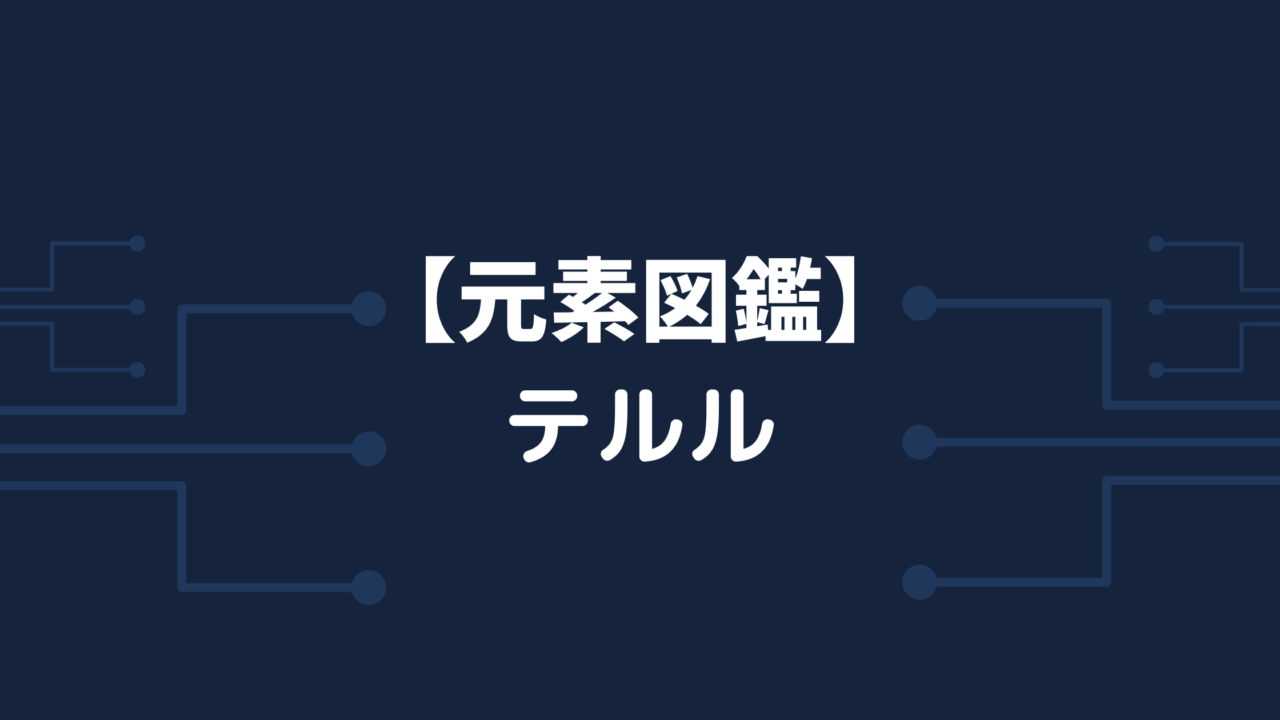
テルルに関する情報をまとめました。
テルルの基本情報
| 和名 | テルル |
|---|---|
| 英名 | Tellurium |
| 語源 | ラテン語「地球(Tellus)」 |
| 元素記号 | Te |
| 原子番号 | 52 |
| 原子量 | 127.6 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体 |
| 色 | 銀灰色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 6.240 g/cm3(20℃) |
| 融点 | 449.8℃ |
| 沸点 | 991℃ |
| 発見者 | ライフェンシュタイン(オーストラリア), クラップロート(ドイツ)[1798年] |
| 含有鉱物 | カラヴェラス鉱 |
テルルの主な特徴
- 原子番号52の半金属元素(メタロイド)で、周期表16族(カルコゲン)に属す
- 銀白色の金属光沢を持ち、もろく壊れやすい性質がありますが、導電性や熱伝導性も示すなど、金属と非金属の中間的性質を持つ
- 自然界では遊離状態ではほとんど存在せず、金属鉱石中に微量のテルル化物として含まれる
- 結晶構造は三方晶系で、セレンや硫黄と同様にポリマー状の鎖構造を持つ場合もある
テルルの歴史
発見
テルルは1782年にオーストリアの鉱物学者フランツ=ヨーゼフ・ミュラー(Franz-Joseph Müller von Reichenstein)によって、金鉱石中から未知の元素として報告されました。
その後、1798年にドイツの化学者マルティン・クラプロート(Martin Heinrich Klaproth)が元素としての存在を確認し、命名を行いました。
名前の由来
「テルル」という名称は、ラテン語の「tellus(大地)」に由来しており、地球に由来する元素という意味が込められています。
テルルの主な用途
テルルはその化学的・電子的特性を活かし、以下のような用途で利用されています:
- 熱電材料: ビスマステルル化合物(Bi₂Te₃)は熱電冷却素子・発電素子として広く利用
- 金属合金添加剤: 鋼や鉛への添加により機械加工性や耐食性を向上
- 光記録材料: DVD-RAMやBlu-rayなどの相変化記録メディアの材料(Ge-Sb-Te系)
- 太陽電池材料: CdTe(テルル化カドミウム)は薄膜太陽電池の光吸収層として使用
- ゴム・化学触媒: 硫黄化合物の調整や反応促進剤としての役割も担う
テルルの生成方法
テルルは主に以下の方法で生産されます:
- 銅精錬の副産物: 電解製錬のアノードスライムから、テルルを含む化合物が回収される
- 酸化・還元処理: 精製されたテルル酸塩を還元して金属テルルを得る
世界的な生産量は多くなく、主要な生産国は中国、アメリカ、日本、カナダなどです。
テルルを含む化合物
テルルは−2価、+4価、+6価を取り、多彩な化合物を形成します。主なものには以下があります:
- H₂Te(テルル化水素): 揮発性の毒性ガスで還元剤。硫化水素と類似
- TeO₂(二酸化テルル): 光学ガラス材料や非線形光学材料として応用
- CdTe(テルル化カドミウム): 薄膜太陽電池用半導体材料
- Bi₂Te₃(ビスマステルル): 熱電変換材料として広く実用化
- Ge-Sb-Te系化合物: 相変化記録媒体のコア素材
テルルに関わる研究事例
テルルを用いた研究は以下の分野で活発に進められています:
- 熱電変換材料の高効率化: Bi₂Te₃のナノ構造化、合金化、層状構造制御による性能向上
- トポロジカル絶縁体: Bi₂Te₃やSb₂Te₃は代表的な3次元トポロジカル絶縁体として物性物理分野で注目
- CdTe太陽電池の高変換効率化: 電荷移動層やドーピング制御に関する研究が進行
- 光相変化メモリ: GeTe-SbTe系材料の高速・高耐久性デバイスへの応用
- 毒性・環境影響評価: テルルの生体毒性に関する環境分析や安全性評価も重要な研究課題
参考図書
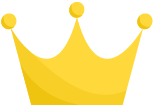 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
リンク
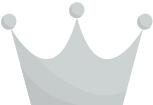 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
リンク
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。
リンク