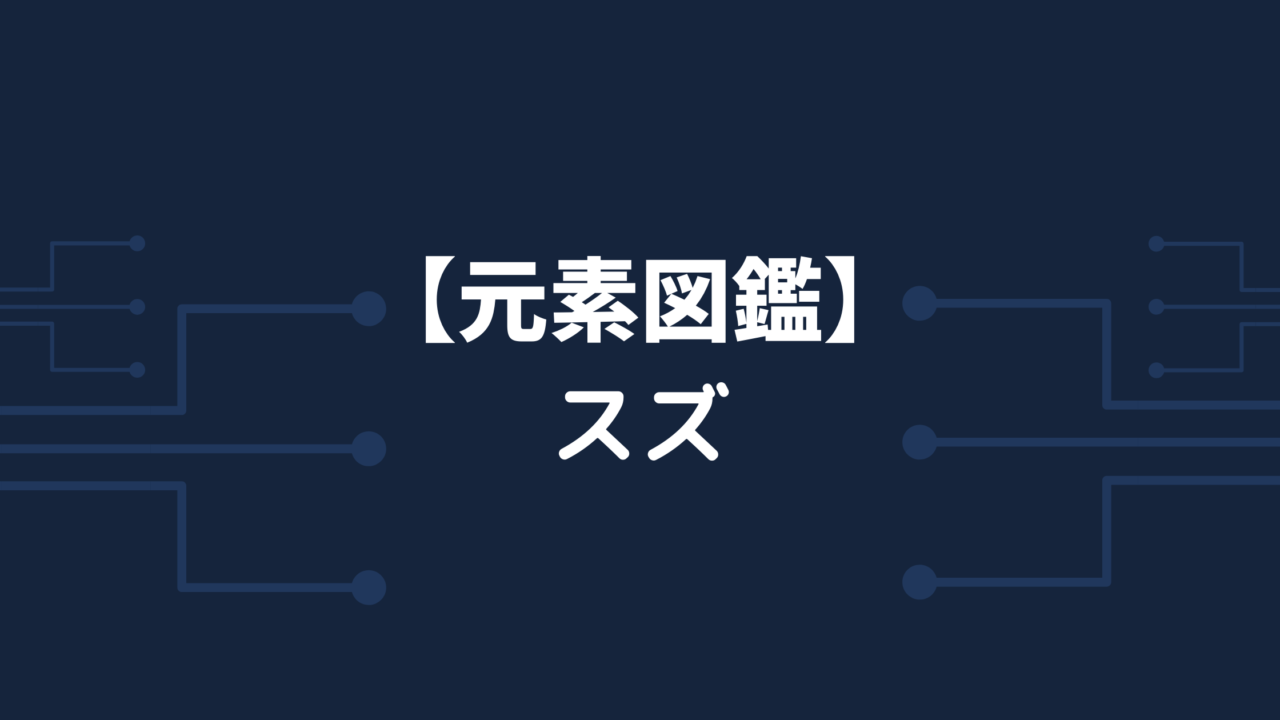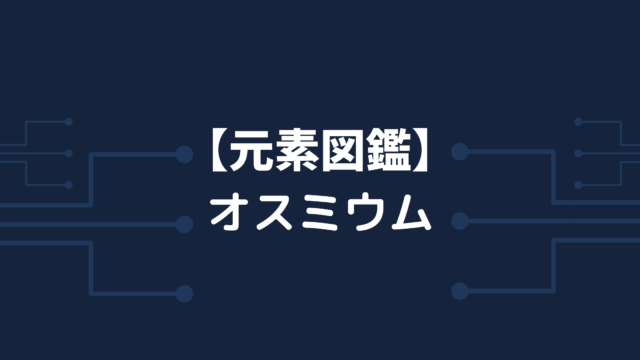スズに関する情報をまとめました。
基本情報
和名:スズ
英名:Tin
語源:エトルリア文明の明るい空の神 (Tinia)
元素記号:Sn
原子番号:50
原子量:118.7
常温(25℃)での状態:固体(金属)
色:白色
密度:5.750 g/cm3(白色スズ)
融点:231.968℃
沸点:2603℃
発見者:古来より知られている
含有鉱物:錫石
スズの基本情報
| 和名 | スズ |
|---|---|
| 英名 | Tin |
| 語源 | エトルリア文明の明るい空の神 (Tinia) |
| 元素記号 | Sn |
| 原子番号 | 50 |
| 原子量 | 118.7 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 白色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 5.750 g/cm3(白色スズ) |
| 融点 | 231.968℃ |
| 沸点 | 2603℃ |
| 発見者 | 古来より知られている |
| 含有鉱物 | 錫石 |
スズの主な特徴
- 原子番号50の金属元素で、周期表14族に属す
- 銀白色で柔らかく、延性に富む金属で、空気中では酸化皮膜を形成して内部を保護する
- 融点は231.9°Cと比較的低く、古代より合金材料(青銅)や表面処理材(ブリキ)として利用されてきた
- 低温で金属スズ(β-スズ)から灰色スズ(α-スズ)に転移する「スズペスト」現象でも知られている
スズの歴史
発見
スズは古代より人類に知られていた元素のひとつで、紀元前3000年ごろのメソポタミア文明では、銅とスズを混ぜた青銅(ブロンズ)が製造されていました。
単体としてのスズも早期に精錬されており、錫器や鋳物として広く用いられてきました。
名前の由来
元素記号Snは、ラテン語の「stannum(スズ)」に由来します。
英語名の「Tin」や日本語の「スズ」はゲルマン語系の語源を持ちますが、どちらも古代からの伝統的な名称です。
スズの主な用途
スズは、その化学的安定性と融点の低さを活かして以下のように利用されています:
- はんだ材料: 鉛との合金(Sn-Pb)はんだや、鉛フリーはんだ(Sn-Ag-Cuなど)の主成分
- ブリキ: 鋼板にスズを薄くメッキした耐食材料。缶詰など食品容器に利用
- 合金材料: 青銅(銅-スズ)、バビットメタル(軸受用)、はんだ合金などの構成成分
- 化学薬品: スズ化合物は触媒や安定剤、還元剤として利用(例:塩化スズ)
- 導電ペースト・電極材料: フレキシブル電子回路、太陽電池などにも応用が進む
スズの生成方法
スズは主にスズ石(SnO₂)として自然界に存在し、以下の工程で精製されます:
- 還元法: スズ石を炭素(コークス)で高温還元して金属スズを得る
- 精製: 溶融精製や電解精製によって高純度スズを製造
世界的な産出国は中国、インドネシア、ミャンマー、ペルーなど。リサイクルも進んでおり、はんだ屑やブリキの再生利用も重要です。
スズを含む化合物
スズは+2価および+4価の酸化状態をとり、さまざまな化合物を形成します:
- SnCl₂(塩化スズ(II)): 還元剤、鏡面反応やメッキに利用
- SnCl₄(塩化スズ(IV)): 触媒や有機合成中間体に使用
- SnO(酸化スズ(II)): 電子材料やガラスコーティング材
- SnO₂(酸化スズ(IV)): ガスセンサ材料、導電性薄膜(FTOガラス)に利用
- 有機スズ化合物: 安定剤、農薬、防汚塗料など(現在は毒性問題により規制あり)
スズに関わる研究事例
スズに関する研究は以下のような分野で進行しています:
- 鉛フリーはんだ開発: 高信頼性・低融点のSnベースはんだ合金の組成・界面解析
- スズ系半導体: SnSやSnSeの光電変換材料としての可能性(非毒性・低コスト)
- スズ酸化物ガスセンサ: SnO₂を用いた高感度VOCセンサの設計
- ペロブスカイト太陽電池: Sn²⁺を用いた鉛フリー型ペロブスカイトの研究
- スズペストの抑制: 低温域での相転移を抑制するための合金化技術
参考図書
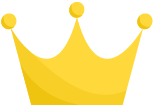 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
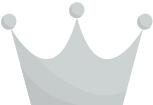 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。