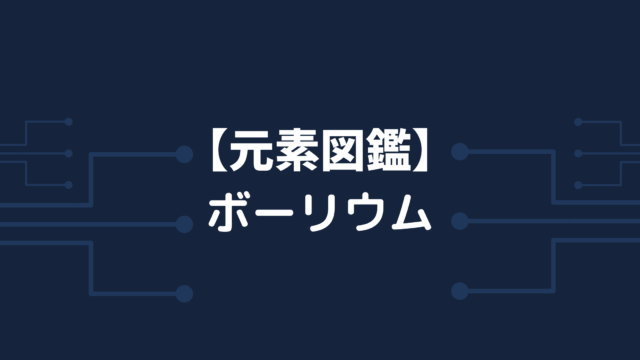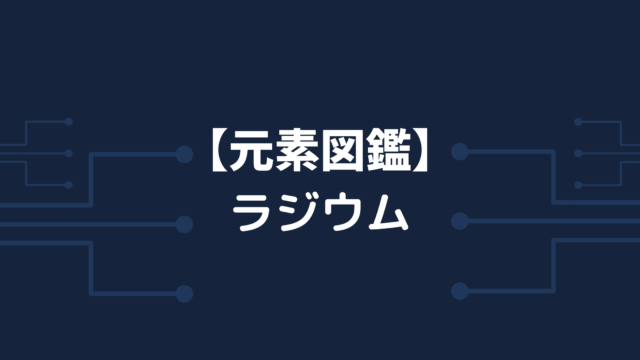【元素図鑑】カドミウム Cd【イタイイタイ病の原因】
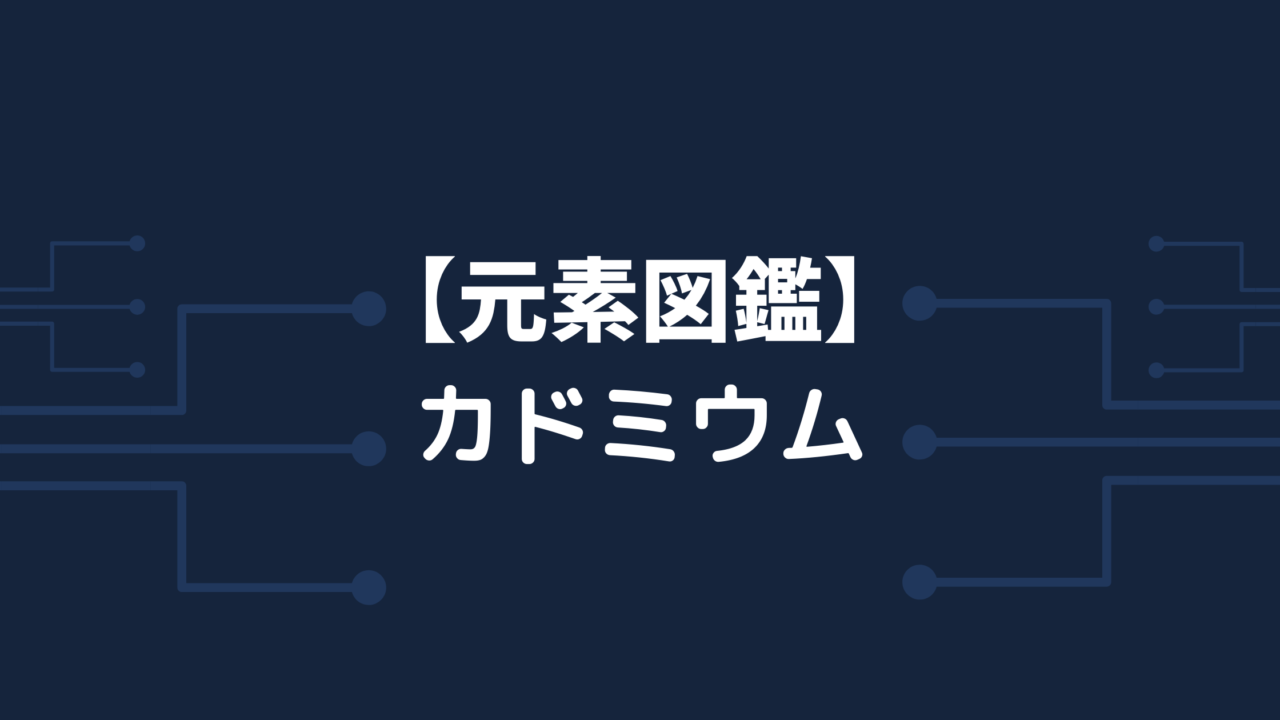
カドミウムに関する情報をまとめました。
カドミウムの基本情報
| 和名 | カドミウム |
|---|---|
| 英名 | Cadmium |
| 語源 | フェニキア神話の王子カドムス (Cadmus) |
| 元素記号 | Cd |
| 原子番号 | 48 |
| 原子量 | 112.4 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 銀白色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 8.650 g/cm3 |
| 融点 | 321.03℃ |
| 沸点 | 767℃ |
| 発見者 | シュトロマイヤー(ドイツ)[1817年] |
| 含有鉱物 | 菱亜鉛鉱(̚カドミア) |
カドミウムの主な特徴
- 原子番号48の遷移金属元素で、周期表第12族に属す
- 銀白色の柔らかい金属で、融点が低く、化学的には亜鉛(Zn)に類似している
- 常温では比較的安定ですが、加熱すると有毒な酸化カドミウム(CdO)の煙を発生させるなど、強い毒性を持つため取り扱いには注意が必要
- 電子部品や電池、顔料などに利用されてきた工業的に重要な金属
カドミウムの歴史
発見
カドミウムは1817年、ドイツの化学者フリードリヒ・シュトロマイヤー(Friedrich Stromeyer)によって発見されました。
亜鉛化合物を精製していた際、従来知られていたものとは異なる性質を持つ不純物の存在に気づき、新元素として単離しました。
同年、カール・ヘルマン(Karl Samuel Leberecht Hermann)も独自に同元素を報告しています。
名前の由来
元素名「カドミウム(Cadmium)」は、ラテン語の「cadmia(亜鉛鉱)」に由来します。
古代では亜鉛鉱から採取された物質を「cadmia」と呼んでおり、カドミウムがこの鉱石の副産物として発見されたことにちなみます。
カドミウムの主な用途
カドミウムは毒性を持つ一方で、以下のような用途で工業的に利用されてきました:
- ニカド電池(Ni-Cd): ニッケルと組み合わせて、充電式電池の負極に使用(現在はリチウムイオン電池に代替されつつある)
- 顔料: 硫化カドミウム(CdS)を使った「カドミウムイエロー」や「カドミウムレッド」は発色が鮮やかで耐光性に優れる
- 防食合金: 鉄や鋼材の表面にメッキし、耐食性を高める(航空機部品など)
- 中性子吸収材: 熱中性子をよく吸収するため、原子炉の制御棒や遮蔽材に利用
- 半導体材料: CdTe(テルル化カドミウム)、CdSは太陽電池や光センサー材料として使用
カドミウムの生成方法
カドミウムは天然に単独鉱として存在することは稀であり、主に以下のようにして得られます:
- 亜鉛鉱石(閃亜鉛鉱)からの副産物: 亜鉛の製錬過程で揮発したCdを回収・精製
- 湿式精錬: 電解法や沈殿法により亜鉛溶液からカドミウムを分離
精製後はインゴットや粉末として供給され、電池・顔料・メッキ用などの用途に利用されます。
カドミウムを含む化合物
カドミウムは主に+2価の化合物を形成し、以下のような重要な化合物があります:
- CdS(硫化カドミウム): 黄色の顔料で、光電子材料にも用いられる
- CdTe(テルル化カドミウム): 太陽電池や赤外線検出器の材料として注目
- CdO(酸化カドミウム): 電子材料・顔料・触媒として使用
- CdCl₂(塩化カドミウム): 合成中間体や金属メッキ用
これらの化合物は水溶性が高く毒性が強いため、取り扱いには厳重な管理が必要です。
カドミウムに関わる研究事例
カドミウムに関する研究は以下の分野で進められています:
- Cdフリー材料開発: 毒性回避のため、CdSやCdTeを代替する非毒性材料(ZnS、CuInS₂など)の研究
- 毒性メカニズムの解析: 細胞内のCa²⁺チャネルとの競合、活性酸素生成などによる細胞毒性の解明
- 環境中のCd挙動: 土壌や水中での移動、植物による吸収と蓄積(カドミウム米問題)
- 半導体応用: CdTe系太陽電池の変換効率向上、安定性評価
- リサイクル技術: 使用済みニカド電池からのCd回収と再利用の技術開発
参考図書
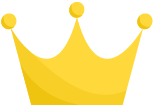 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
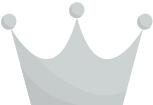 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。