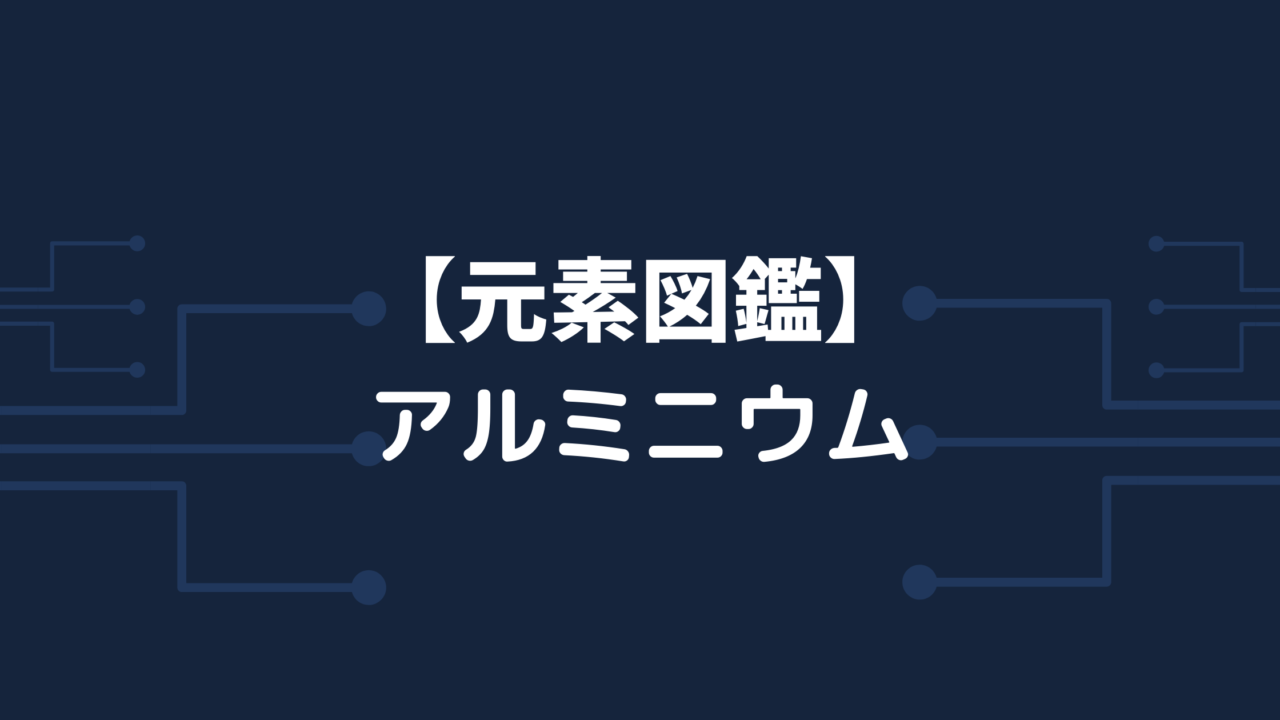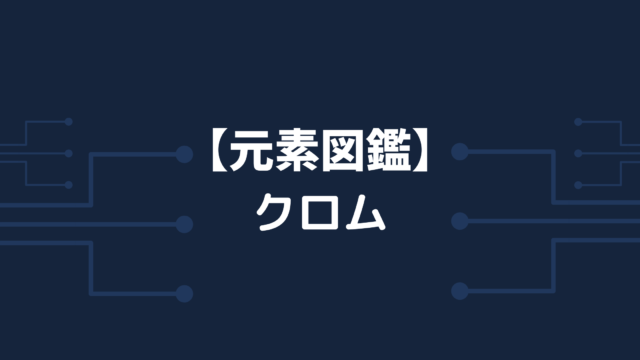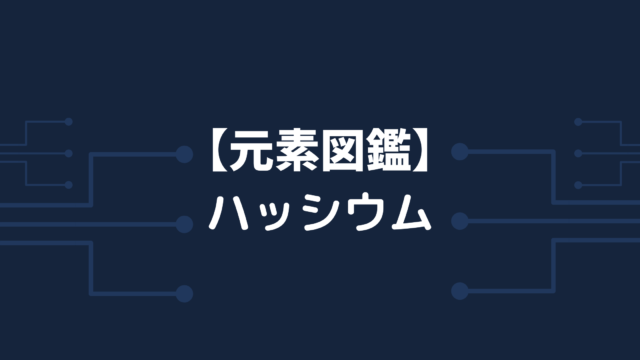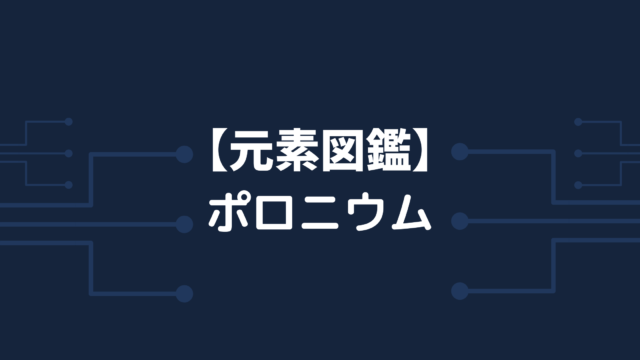アルミニウムに関する情報をまとめました。
アルミニウムの基本情報
| 和名 | アルミニウム |
|---|---|
| 英名 | Aluminium (Aluminum) |
| 語源 | ギリシャ語・ローマ語「ミョウバン(alumen)」 |
| 元素記号 | Al |
| 原子量 | 26.98 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 銀白色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 2.698 g/cm3 (20℃) |
| 融点 | 660.37℃ |
| 沸点 | 2520℃ |
| 発見者 | デービー(イギリス, 1807年) |
| 含有鉱物 | ミョウバン石 |
アルミニウムの主な特徴
- 軽金属元素で、銀白色の柔らかい金属
- 比重は約2.7と軽く、耐食性、導電性、加工性に優れ、現代の産業や日常生活において極めて重要な材料
- 空気中では表面に緻密な酸化皮膜(Al2O3)を自然に形成し、内部の腐食を防ぐ
- 電気や熱をよく通すため、建材・電線・調理器具・包装材料など多岐にわたって活用されてる
アルミニウムの歴史
発見
アルミニウム化合物は古くから知られており、古代ローマでは「明礬(ミョウバン)」として利用されていました。
単体のアルミニウムは1825年、デンマークのハンス・クリスチャン・エルステッドが初めて単離に成功し、
その後フリードリッヒ・ヴェーラーが純度の高い金属を得ました。
しかし、19世紀中頃までは非常に高価な金属で、「銀よりも貴重」とされていました。
名前の由来
「アルミニウム(Aluminium)」という名称は、ラテン語の「alumen(明礬)」に由来します。
イギリス英語では「aluminium」、アメリカ英語では「aluminum」という表記が使われています。
アルミニウムの主な用途
アルミニウムはその軽さ・耐食性・加工性を活かし、以下の分野で広く使用されています:
- 建築資材: サッシ、外装材、屋根材など
- 輸送機器: 航空機、電車、自動車部品の軽量化材料として
- 電気機器: 電線、冷却板、コンデンサーなど電気・熱伝導用途
- 包装材: アルミホイル、缶、レトルトパウチなど
- 調理器具: 鍋、フライパン、炊飯器の内釜など
アルミニウムの生成方法
アルミニウムは自然界に豊富に存在しますが、単体では存在せず、主にボーキサイトから以下の工程で製造されます:
- バイヤー法: ボーキサイトから水酸化ナトリウムでアルミナ(Al2O3)を抽出
- ホール・エルー法: アルミナを氷晶石(Na3AlF6)中に溶かし、高温電解して金属Alを得る
アルミニウムを含む化合物
アルミニウムは主に+3価のイオン(Al3+)として安定した化合物を多数形成します:
- 酸化アルミニウム(Al2O3): 耐火性・耐摩耗性に優れたセラミック材料、人工サファイア
- 硫酸アルミニウム(Al2(SO4)3): 水処理、紙の製造、明礬(ミョウバン)として使用
- 塩化アルミニウム(AlCl3): ルイス酸触媒としてフリーデル・クラフツ反応などに使用
- アルミニウム合金: Al-Cu, Al-Mg, Al-Si系など航空・自動車用の強化材料
アルミニウムに関わる研究事例
アルミニウムは工業だけでなく、材料科学や環境工学、生体応用などの分野でも研究が進められています:
- 高強度・耐腐食性アルミ合金の開発: 航空・宇宙・自動車産業向けの次世代材料
- アルミニウム空気電池: 軽量・高エネルギー密度の電源として期待される新技術
- アルミニウムリサイクル: 環境負荷の小さい再生プロセスの確立と応用
- 生体影響研究: 神経系・腎臓系への影響評価、アルツハイマー病との関連検討
- ナノ構造酸化アルミニウム: 触媒担体、光学材料、医療材料としての応用研究
筆者の薦める1冊
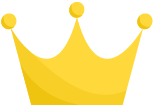 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
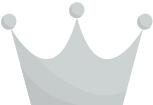 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。