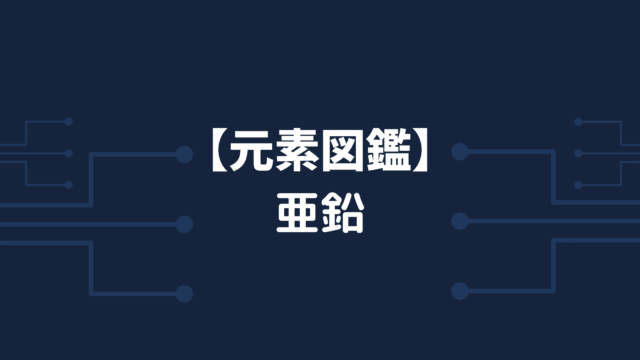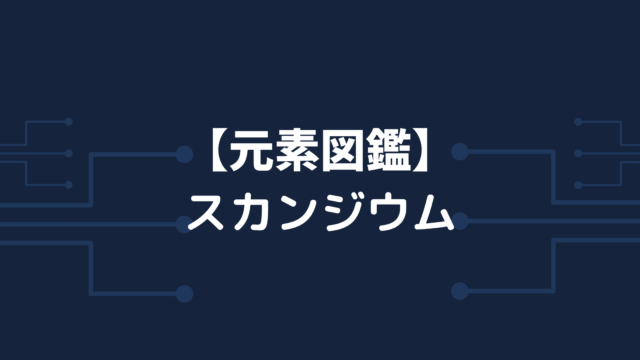リチウムに関する情報をまとめました。
リチウムの基本情報
| 和名 | リチウム |
|---|---|
| 英名 | Lithium |
| 語源 | ギリシャ語 「石(lithos)」 |
| 元素記号 | Li |
| 原子番号 | 3 |
| 原子量 | 6.941 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 銀白色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 0.534 g/L (0℃) |
| 融点 | 180.54℃ |
| 沸点 | 1347℃ |
| 発見者 | アルフェドソン(スウェーデン)[1817年] |
| 含有鉱物 | ペタル石 |
リチウムの主な特徴
- アルカリ金属
- 最も軽い金属
- 水や空気中の酸素と激しく反応する
- イオン化傾向が大きいことから、電池材料として重要
リチウムの歴史
発見
リチウムは1817年、スウェーデンの化学者ヨハン・アウグスト・アルフェドソンによってペタライト鉱石から初めて発見されました。元素単体としての分離は、その2年後にハンフリー・デービーらによる電気分解によって達成されました。
名前の由来
ギリシャ語 lithos(石) に由来します。鉱石から最初に発見されたためです。
他のアルカリ金属(ナトリウムやカリウム)が植物由来で発見されたのに対し、リチウムは鉱物中から発見されたため、このような命名がなされました。
リチウムの主な用途
リチウムの最大の用途はリチウムイオン電池(Li-ion battery)であり、スマートフォン、ノートパソコン、電気自動車などのエネルギー源として不可欠です。また、以下のような用途もあります:
- リチウム合金(アルミニウム・マグネシウムとの軽量合金)
- 耐熱ガラスやセラミックスの強化剤
- 空調用の吸湿剤(リチウム塩)
- 医薬品(炭酸リチウムは双極性障害の治療薬として使用)
- 核融合研究におけるトリチウムの生成材
リチウムの生成方法
リチウムは自然界に単体では存在せず、主に以下の方法で得られます:
- 鉱石からの抽出:スポジュメン(LiAlSi2O6)やレピドライト(LiAl3(Al,Si)4O10(F,OH)2)などの鉱石から熱処理・酸処理によって抽出
- 塩湖からの濃縮:ボリビア、チリ、アルゼンチンの塩湖から、太陽光で濃縮した塩水から塩化リチウム(LiCl)を取り出す
- 電気分解:LiClなどの融解塩を電気分解して金属リチウムを得る
リチウムを含む化合物
リチウムは多くの化合物を形成し、工業・医療分野で広く利用されています:
- 炭酸リチウム(Li2CO3):精神安定剤として使用されるほか、リチウムイオン電池の原料としても重要
- 水酸化リチウム(LiOH):グリース、アルミ電解、宇宙飛行士の二酸化炭素除去剤に使用
- 塩化リチウム(LiCl):吸湿剤や化学合成用中間体として用いられる
- リチウムアルミニウム水素化物(LiAlH4):有機化学における還元剤
リチウムに関わる研究事例
リチウムに関する研究は非常に活発であり、以下のような事例が挙げられます:
- 次世代電池材料の開発:リチウム硫黄電池や全固体電池(solid-state battery)におけるリチウムの拡散挙動や界面反応の解析
- 宇宙環境におけるリチウムの挙動:宇宙機器におけるバッテリー劣化メカニズムの研究
- 持続可能なリチウム資源開発:海水や地熱水からのリチウム回収法の確立
- 医学研究:リチウムによる神経保護作用や長寿遺伝子の発現への影響を評価する研究
参考図書
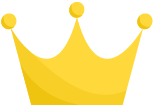 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
リンク
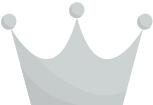 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
リンク
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。
リンク