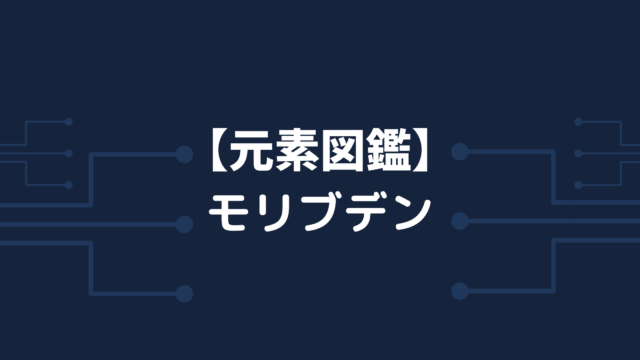【元素図鑑】酸素 O【原子番号8】

酸素に関する情報をまとめました。
酸素の基本情報
| 和名 | 酸素 |
|---|---|
| 英名 | Oxygen |
| 語源 | ギリシャ語 「酸(oxys)+源(gennao)」 |
| 元素記号 | O |
| 原子量 | 16.00 |
| 常温(25℃)での状態 | 気体 |
| 色 | 無色 |
| 臭い | 無臭 |
| 密度 | 1.429 g/L (気体, -0.15℃) |
| 融点 | 180.54℃ |
| 沸点 | 1347℃ |
| 発見者 | シェーレ(スウェーデン, 1771年), プリ―ストリー(イギリス, 1774年) |
| 含有鉱物 | フッ素魚眼石 |
酸素の主な特徴
- 常温常圧では無色・無臭の気体
- 生物の呼吸や燃焼反応に不可欠な元素
酸素の歴史
発見
酸素は1774年にイギリスの化学者ジョセフ・プリーストリーによって発見されました。同時期にスウェーデンのカール・シェーレも独立に酸素を発見していましたが、プリーストリーの方が先に発表したことで名が知られています。
名前の由来
フランスの化学者アントワーヌ・ラヴォアジエが命名したもので、ギリシャ語の「oxys(酸っぱい)」と「genes(生じる)」に由来します。当時、酸の本質が酸素にあると考えられていたことに由来します。
酸素の主な用途
酸素は医療用酸素として呼吸補助に使われるほか、工業分野では高炉での鉄の精錬、ロケット燃料用の液体酸素(LOX)、化学合成における酸化剤など、幅広く使用されています。
また、水族館や水槽などでは溶存酸素の補給にも使われます。
酸素の生成方法
酸素は以下のような方法で得られます:
- 空気の分留:液化空気を蒸留することで高純度の酸素を得る。
- 過酸化水素の分解:
2H2O2 → 2H2O + O2(触媒にMnO2) - 塩素酸カリウムの熱分解:
2KClO3 → 2KCl + 3O2(触媒にMnO2)
酸素を含む化合物
酸素は多くの化合物を形成します。代表的なものは以下の通りです:
- 水(H2O):酸素と水素の化合物。生命に不可欠。
- 二酸化炭素(CO2):炭素と酸素の化合物。呼吸や燃焼によって発生。
- オゾン(O3):酸素の同素体。紫外線を吸収し、成層圏で重要な役割を果たす。
- 酸化鉄(Fe2O3など):鉄と酸素の化合物。さびの主成分。
酸素に関わる研究事例
酸素は多くの研究対象として扱われています。たとえば:
- 生体内での酸素の挙動を調べるために、近年ではMRIや蛍光プローブを用いたイメージング研究が進んでいます。
- 人工光合成では、水の酸化による酸素発生反応(OER:Oxygen Evolution Reaction)の高効率化が重要課題です。
- 航空宇宙工学においては、液体酸素を推進剤としたロケット燃料系の改良も注目されています。
筆者の薦める1冊
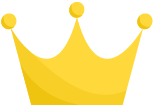 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
リンク
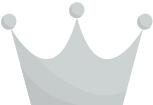 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
リンク
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。
リンク