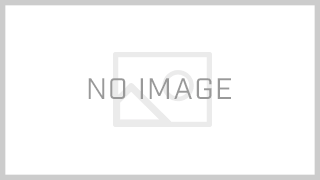アミド官能基の構造・性質・合成・反応・ペプチド結合まで徹底解説
アミド(amide)は、カルボン酸誘導体の一つであり、カルボニル基(C=O)にアミノ基(–NH2)が結合した構造を持つ官能基です。
その構造の安定性と反応性の絶妙なバランスから、有機合成・高分子化学・生化学において極めて重要な位置を占めています。
特に、生体内ではアミド結合がタンパク質の主鎖(ペプチド結合)を構成しており、生命の基本構造を支えています。
アミドの構造と命名法
アミドは、一般にR–CONH2(第一級アミド)、R–CONHR’(第二級アミド)、R–CONR’R”(第三級アミド)と表記され、カルボニル炭素にアミノ基が直接結合しています。
IUPAC命名法
- カルボン酸に相当する部分の語尾を「-amide(アミド)」に変える
- 第二級・第三級アミドでは、Nに結合する置換基を「N-」で修飾
命名例
- CH3CONH2 → ethanamide(アセトアミド)
- CH3CONHCH3 → N-methyl ethanamide
- CH3CON(CH3)2 → N,N-dimethyl ethanamide
アミドの分類
- 第一級アミド: –CONH2(2つの水素を持つ)
- 第二級アミド: –CONHR(1つの水素 + 1つのアルキル)
- 第三級アミド: –CONRR’(水素なし、2つの置換基)
この分類は、アミンの分類と同様ですが、アミドでは電子の共鳴構造が関与するため、物性・反応性に大きく影響します。
アミドの構造的特徴と安定性
共鳴安定化
アミドは、孤立電子対を持つN原子がC=Oと共鳴構造を形成することで、部分的な二重結合性を持ちます。
これにより:
- 回転障害が発生(単結合であっても自由に回転できない)
- 酸素と窒素の間に電荷の偏りが減少し、安定化される
極性と水素結合
- 高い極性と水素結合能力を持つ(特に第一級・第二級アミド)
- 比較的高い融点・沸点を示す
アミドの主な合成法
① 酸塩化物または無水物 + アミン
R–COCl + R'NH₂ → R–CONHR' + HCl最も一般的で高収率。塩基(例:ピリジン)を加えてHClを中和します。
② カルボン酸 + アミン(脱水剤必要)
直接反応は水生成により不利なため、DCC(ジシクロヘキシルカルボジイイミド)などの脱水縮合剤を使用
③ エステルからの変換
R–COOR' + NH₃ → R–CONH₂ + R'OH④ アシルアジド経由(Curtius反応)
イソシアネート中間体を経由してアミド・ウレアなどに変換
アミドの主な化学反応
① 加水分解(酸性または塩基性)
- アミド + H2O → カルボン酸 + アミン
- 酸または塩基の加熱条件で進行
② 還元反応
- LiAlH4によりアミンに還元(R–CONH2 → R–CH2NH2)
- ホルモアミドからメチルアミンなども合成可
③ 脱水によるニトリル形成
強力な脱水剤を用いることで、アミド → ニトリル(R–C≡N)
④ アミド転移反応
条件に応じてアミノ部分を他の置換基へ転移可能(N-アルキル化など)
アミドの生体分子における役割
① ペプチド結合
アミノ酸がカルボン酸 + アミノ基の縮合によって形成する結合がペプチド結合です。
これはまさにアミド結合であり、タンパク質の主鎖骨格を構成しています。
- 非常に安定(加水分解には酵素や強酸/塩基が必要)
- 平面構造を保ち、タンパク質の高次構造に寄与
② 核酸や酵素でも類似の結合が存在
酵素活性部位などでアミド基が反応に関与する例もあります
アミドの応用例
- 薬品(アセトアミノフェン、ペニシリンなど)
- 材料(ポリアミド:ナイロン)
- 溶媒(ジメチルアセトアミド、DMF)
- プロドラッグ設計における安定性制御
まとめ:アミドは生命と材料を支える官能基
- アミドはカルボン酸 + アミンから形成される安定な構造
- 共鳴により構造的に非常に安定(回転障害など)
- 加水分解・還元・転移などの反応性あり
- 生体内ペプチド結合、材料化学、医薬品などに広く応用
次回は、「ニトリル(–C≡N)」をテーマに、電子特性・反応性・合成法・応用などについて詳しく解説します。
🧭 関連リンク
- 👉 【まとめ記事】官能基シリーズ 一覧はこちら
- 👉 【第4回】エステル官能基
- 👉 【第6回】ニトリル官能基(近日公開)