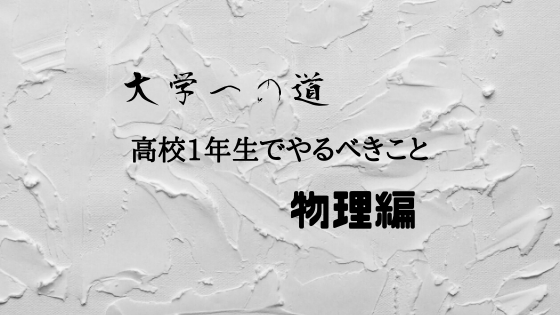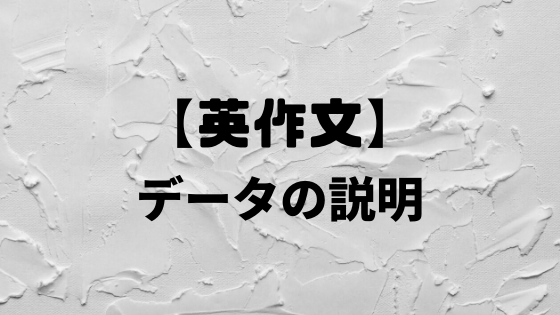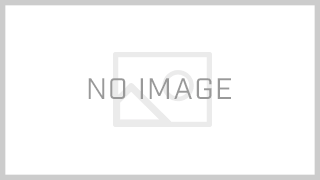【第8章】 付加反応のメカニズムとその応用例:アルケン・アルキン・カルボニル化合物を中心に解説
有機化学における付加反応(addition reaction)は、二重結合や三重結合などのπ結合をもつ化合物に新たな原子団が加わる反応を指します。付加反応は、炭素骨格の修飾や官能基の導入において極めて重要な役割を果たします。
この章では、アルケン・アルキンの付加反応に加え、カルボニル化合物(C=O)に対する求核付加などの代表的な反応を分類・整理し、それぞれの反応機構、立体化学、反応選択性、そして実用的な応用例について解説していきます。
付加反応の基本概念
付加反応とは、π結合の破壊とσ結合の形成によって進行する反応で、次のような特徴があります。
- 不飽和結合(C=C, C≡C, C=O)に対して起こる
- 2つの原子や官能基が結合する
- 中間体としてカルボカチオン・ラジカル・環状構造が生じることもある
付加反応の主な分類
- 電解質的付加(酸・ハロゲンの付加)
- 求核付加(カルボニル化合物へのアタック)
- 還元的付加(水素化)
- 酸化的付加(ヒドロホウ素化・ジヒドロキシル化など)
アルケンの付加反応
① ハロゲン化水素(HX)の付加
アルケンにHCl、HBr、HIなどを付加する反応です。マルコフニコフ則に従い、より多くの置換基を持つ炭素にXが付加します。
CH₂=CH₂ + HBr → CH₃–CH₂Brマルコフニコフ則
電気的に中性な試薬が非対称なアルケンに付加する場合、より安定なカルボカチオン中間体を形成する経路で進行します。
② 水の付加(酸触媒加水分解)
CH₃–CH=CH₂ + H₂O (H⁺) → CH₃–CH(OH)–CH₃この反応もマルコフニコフ則に従います。カルボカチオン中間体を経由するため、転位やラセミ化も生じる可能性があります。
③ ヒドロホウ素化(BH₃)→ 酸化
CH₂=CH₂ + BH₃ → CH₃CH₂BH₂
→ CH₃CH₂OH(酸化により)アンチマルコフニコフ付加が起こり、ヒドロキシ基がより水素の多い炭素に結合します。立体的にはシン付加(同じ面からの付加)です。
④ ハロゲン(Br₂、Cl₂)の付加
アルケンにBr₂を反応させると、ハロニウムイオン中間体を経て、アンチ付加が起こります。
CH₂=CH₂ + Br₂ → BrCH₂–CH₂Brアルキンの付加反応
アルキンはπ結合が2本あるため、付加反応が2回連続で起こることがあります。
① 水素化(H₂ + Pd/C)
部分水素化(Lindlar触媒)を使えば、シス-アルケンを得ることができます。
② HXの付加
2当量加えると、ビニルジハロ化合物が得られます。
③ 水の付加 → ケトン生成(Keto-enol Tautomerism)
Hg²⁺触媒下での水の付加により、エノールを経てケトンに変換されます。
カルボニル化合物への求核付加
C=O基(カルボニル基)は、Oが電気陰性度が高く電子を引っ張るため、Cが求電子中心となります。ここに求核剤が電子を提供して結合するのが求核付加反応です。
① ヒドリド還元
R–C=O + NaBH₄ → R–CH₂OH② グリニャール反応(RMgX)
R–C=O + RMgBr → R–C(OH)–R'③ シアン化物イオンの付加
R–C=O + CN⁻ → R–C(CN)(OH)このような付加反応は、アルデヒド・ケトンをアルコールや新しいC–C結合を持つ化合物へ変換する上で重要です。
立体化学と選択性
- シン付加: 両置換基が同じ面に結合(例:ヒドロホウ素化)
- アンチ付加: 両置換基が反対側に結合(例:Br₂付加)
また、マルコフニコフ則・アンチマルコフニコフ則の選択性も、反応の設計において重要な指針となります。
付加反応の応用例
① アルコールの合成
- アルケンにH₂O(酸触媒)→ 中間アルコール
- カルボニル基へのNaBH₄還元 → アルコール
② 炭素–炭素結合の形成
- グリニャール反応
- シアン化物による付加
③ 官能基導入による反応性の変化
- カルボニルへの付加 → ヒドロキシ基 → さらなる誘導体合成へ
まとめ:付加反応は有機化学の展開力を支える
- 付加反応は、π結合をもつ分子に原子団が加わる基本的な変換
- アルケン・アルキン・カルボニル化合物で特に重要
- 立体化学や選択性(マルコフニコフ則)にも注意
- 反応例を通じて、反応設計・合成応用にも活かされる
次章では、付加反応以外の有機反応タイプとして、酸化・還元反応を中心に学びます。電子数の増減に注目したアプローチで、アルコール・ケトン・カルボン酸の変換を読み解いていきましょう。