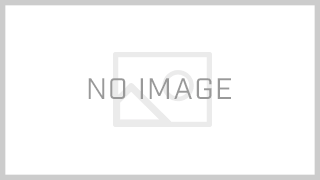ここまでの章で、有機化学の構造、反応、機構を一通り学んできました。
この第10章では、これまでの知識を総動員して「化合物をどう作るか?」という視点から、有機化学を考えていきます。
合成計画(Synthetic Planning)は、実験の前にゴール(標的化合物)から逆算してルートを考える思考法です。さらに、反応が多数ある中で「どれを選ぶべきか?」を決める際には、反応選択性の理解が不可欠になります。
この章では、以下の内容を解説します:
- 反応選択性の3種類:化学選択性・立体選択性・位置選択性
- 逆合成の考え方
- 合成計画の立て方と実践的な例
Contents
反応選択性とは何か?
反応選択性とは、複数の反応経路・生成物が可能なときに、どの経路が優先されるかという現象を指します。これを制御できると、望む化合物だけを効率よく合成できるようになります。
① 化学選択性(Chemoselectivity)
- 同一分子内に異なる官能基があるとき、どの官能基が優先して反応するか
- 例:アルコールとアルデヒドがある分子で、アルデヒドのみを還元する
② 位置選択性(Regioselectivity)
- 同じ官能基でも、分子内のどの位置に反応が起こるか
- 例:アルケンへのHX付加で、マルコフニコフ則に従って特定の炭素に結合する
③ 立体選択性(Stereoselectivity)
- 生成物に立体異性体が複数生じうる場合、どちらが優先されるか
- 例:シス体とトランス体のうち、トランス体が優先して生成する
④ 立体特異性(Stereospecificity)
- 出発物質の立体構造に応じて、生成物の立体が決定される
- 例:SN2反応におけるワルデン反転
逆合成とは?
逆合成(retrosynthesis)は、「この分子をどうやって作ればよいか?」を逆方向(生成物 → 出発物質)にたどる思考法です。
この方法は、1970年代に有機化学者E. J. Coreyが体系化し、ノーベル化学賞を受賞したことで有名になりました。
基本手順
- 標的化合物(Target molecule)を設定する
- 官能基・骨格・結合に注目して、「切断」する
- 得られた断片(synthons)から、合成可能な実在化合物(reagents)を検討する
- 実際の順方向の反応として再構成する
例:2-ブタノールのレトロシンセシス
2-ブタノール → (還元) → 2-ブタノン → (求核攻撃) → ブロモブタン + グリニャール試薬このように、「どこで切るか」「どの反応を使うか」の判断には、反応性と選択性の知識が必要です。
合成計画の立て方
① 官能基変換を整理する
- どの官能基からどの官能基へ変換できるかを把握しておく
- 例:アルコール → アルデヒド → カルボン酸 → アミド → アミン
② 骨格構築の鍵反応を選ぶ
- 炭素–炭素結合形成:アルキル化、求核付加、縮合反応など
③ 合成可能性と実現性を検討する
- 試薬が市販か?反応条件は穏やかか?副反応は?
合成戦略の具体例
例1:4-フェニル-2-ブタノールの合成
標的化合物:Ph–CH₂–CH₂–CH(OH)–CH₃
- アルコールをケトンに酸化(レトロ)
- C=Oへの求核攻撃 → グリニャール反応
- ケトン前駆体の設計 → フェニルエチルケトン
例2:エステルの合成
標的化合物:R–COO–R’
- カルボン酸とアルコールのエステル化(Fischer反応)
- 脱水剤を使って平衡を右に引く
合成設計の練習法
- 教科書にある「逆合成問題」を解いてみる
- 構造式を見て「どこで切れるか?」を考える
- 機能性基に注目する(C=O, OH, NH₂など)
- 選択性の知識と反応パターンの引き出しを増やす
まとめ:有機化学の“思考力”を鍛える
- 反応選択性を理解することで「どの反応が起こるか」を予測できる
- 合成計画では、ゴールから逆にたどる発想(レトロシンセシス)が鍵
- 構造・反応性・条件を結びつけて、論理的にルートを設計する
- 知識だけでなく、“考える力”が問われる段階に進む章
次章では、有機化学のより実践的な分野として、スペクトル解析(NMR・IR・MS)による構造決定の基礎に進みます。