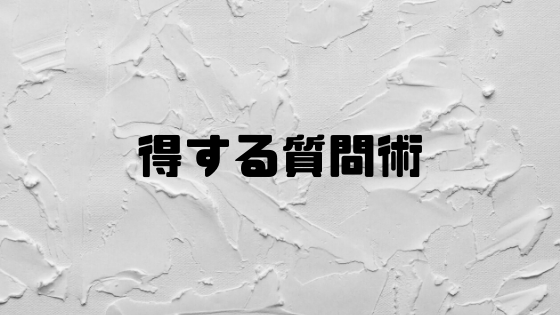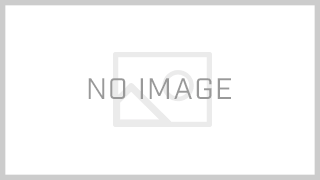【第6章】有機反応の機構とは?電子の流れ・矢印の書き方・反応の分類まで徹底解説
有機化学では、分子がどのように変化していくかを「反応機構(reaction mechanism)」で示します。反応機構は、分子内の電子がどこからどこへ動いたのかを追跡することで、なぜその反応が起こるのか、どのような中間体を経由するのかがわかる強力なツールです。
この章では、反応機構を読み解くための基本として、電子の流れの表し方(矢印の書き方)と、代表的な反応の分類(置換・脱離・付加・酸化還元)をわかりやすく整理していきます。ここをマスターすれば、有機化学の世界が一気に論理的に見えるようになります。
反応機構とは何か?
反応機構とは、化学反応がどのように進行するのかを、原子と電子のレベルで段階的に示したものです。
- どの結合が切れて、どの結合ができるのか
- 中間体や遷移状態はどうなっているか
- 電子がどのように動いているか(電子対の移動)
反応機構がわかれば、「なぜこの生成物になるのか?」という疑問が論理的に説明できるようになります。単なる暗記から、理解と応用への第一歩です。
電子の流れと矢印の意味
有機化学では、電子の流れを湾曲した矢印(曲矢印)で表します。この矢印の向きと始点・終点を正しく理解することが最重要です。
曲矢印(Curved Arrow)の使い方
- 始点:電子のある場所(非共有電子対や結合)
- 終点:電子が移動する先(原子や新たな結合)
例えば、求核剤の非共有電子対が電子不足の炭素に向かって攻撃する場合、その電子の動きを矢印で示します。
Nu: → C⁺矢印1本で電子対2個の移動を表します。これは反応の根幹です。
片矢印(Radical Arrow)
ラジカル反応では、電子1個の移動を表す片矢印(半矢)を使います。
• → •ただし、有機化学初学者にはまず曲矢印(電子対の移動)を中心に理解することが重要です。
電子の流れの基本パターン
① 求核攻撃
電子密度の高い求核剤(Nu⁻)が電子不足の炭素(C⁺)にアタックするパターンです。
Nu⁻ + R–C⁺ → R–C–Nu代表例:SN2反応、エステルの加水分解
② 脱離
電子対が結合から離れ、離脱基(LG)が抜ける反応です。
R–LG → R⁺ + LG⁻代表例:E1脱離反応、脱水反応
③ 結合の生成
電子が2つの原子の間に移動して、新たな共有結合が形成される。
Nu: + E⁺ → Nu–E反応の分類(4大分類)
有機反応は大きく以下の4つに分類されます。それぞれに典型的な反応例があり、今後の学習の基盤になります。
① 置換反応(Substitution)
- ある官能基が別の官能基に置き換わる
- 代表例:SN1、SN2反応
- 例:CH₃Br + OH⁻ → CH₃OH + Br⁻
② 脱離反応(Elimination)
- 分子から2つの原子団が除去されて、二重結合などが生成される
- 代表例:E1、E2反応
- 例:CH₃CH₂Br + base → CH₂=CH₂ + HBr
③ 付加反応(Addition)
- π結合に対して原子や官能基が加わる
- 代表例:アルケンへのHBrの付加
- 例:CH₂=CH₂ + HBr → CH₃CH₂Br
④ 酸化還元反応(Redox)
- 電子の授受を伴う反応
- 有機化学ではC–H → C=Oの変化が酸化、C=O → C–OHの変化が還元
- 代表例:アルコールの酸化、カルボン酸の還元
反応機構の読み解きのコツ
- 電子の偏り(極性)を見る
- 電荷・中性をバランスよく保つ
- 安定な中間体(カルボカチオン、共鳴構造など)を想定する
- 酸・塩基・求核・求電子の役割を意識する
1つの反応を覚えるよりも、なぜそう動くのか?の背景を矢印で説明できるようになることが、有機化学を「使える知識」にする鍵です。
まとめ:反応機構がわかれば有機化学は怖くない
- 反応機構は「電子の動き」を矢印で表すことで反応の流れを可視化する手段
- 湾曲矢印で電子対の移動を正しく示すことが基本
- 有機反応は主に置換・脱離・付加・酸化還元に分類される
- 構造式を読み解き、電子がどう動くかを想像できれば理解が進む
次章では、こうした反応機構を踏まえた上で、実際の有機反応(置換反応・脱離反応など)を個別に深掘りしていきます。