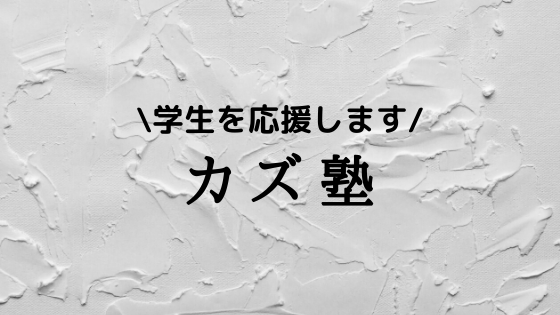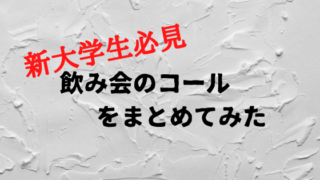機器分析総まとめ【概論】

分子は目で見ることができません。
では、どのようにして合成した分子の構造を確認するのか。
その答えは「機器分析」です。
より具体的に言うと、機器により得られたスペクトルを見て分子の構造を確認します。
つまり、スペクトルを見れば、分子が見えるのです。これが機器分析の目的です。
今回は、機器分析の基礎知識として、代表的な分析機器とその知識を紹介します。
スペクトルから分子が見える化学者を目指していきましょう。
1H NMR
1H NMRは奥が深すぎて、ここでは語り切れません。
ものすごく簡略化して紹介します。
1H NMRでわかること
1H NMRから得られる情報は以下の3つです。
- 化学シフト(δ)
- カップリングとスピン結合定数(J値)
- ピーク面積
化学シフト
原子核の周りは、電子雲で囲まれています。
電子も負電荷を持っているので、外部磁場B0がかかっている状態で原子核の周りを循環すると、反対向きの誘起磁場B’を生じます。
原子核が感じる有効磁場Bはその分だけ減少し、
\[B=B_0–B’\]
と表されます。
これを電子による遮蔽効果と呼びます。
遮蔽効果は、原子核周りの電子密度が大きい場合や環電流効果が働くときに強くなることが知られています。
水素原子核そのものはどれも全く同じ構成ですが、置かれる環境次第で、原子核が感じる磁場の強さが異なります。
その結果、励起波長(=共鳴周波数)に標準からの”ズレ”が生じます。
この”ズレ”こそが化学シフトと呼ばれるものに相当します。
つまり、化学シフトを測定することで、原子核の置かれている環境情報が得られるのです。
通常の1H-NMR測定における化学シフト値は、テトラメチルシラン(TMS)のメチル基を基準(δ=0)とした相対値として、ppmスケールで記録されます。
過去の測定事例から、どのような部分構造がどのような化学シフト値を示すのかについても、だいたいの目安が知られています。
カップリングとスピン結合定数
化学的に非等価な核種同士が近傍に存在するとき、両者は互いに影響しあい、エネルギー準位の分裂を生じます。これがカップリングと呼ばれる現象です。
1H-NMRチャート上では、プロトンHaの隣にn個の等価プロトンHbが存在すると、Haのピーク山が(n+1)本に分裂して観測されます。それぞれのピークは、山の本数によって以下の記号で表記されます。
一重線:シングレット(singlet, s)
二重線:ダブレット(doublet, d)
三重線:トリプレット(triplet, t)
四重線:カルテット(quartet, q)
五重線:キンテット(quintet, quin)
六重線:セクテット(sextet, sex)
七重線:セプテット(septet, sep)
八重線:オクテット(octet)
九重線:ノネット(nonet)
幅広線:ブロード (broad, br)
Hbの隣には化学的等価なHaが2つ存在する場合、Hbのピークは2+1=3本に分かれたトリプレット(t)となります。逆にHaから見ると隣のHbは1つなので、Haのピークは1+1=2本に分かれたダブレット(d)となります。
またカップリングしたピーク山同士の間隔は、スピン結合定数(J値)として記述されます。
カップリングしている各種同士は、全く同じ値のJ値を共有するので、J値はどの核種同士が近接しているかを知る指標になります。J値は以下の式で計算されます。
J (Hz) = 測定周波数 (Hz)x 化学シフト差分(Δδ, ppm)
例えば500MHzの装置で1H-NMRを測定し、化学シフト差分Δδ= 0.015 ppmと計算される場合では、J値は\((500\times106)\times(0.015\times10^{-6})=7.5 Hz\)と計算できます。
ピーク面積
フーリエ変換後に得られる各ピークの面積値は、核種の存在比に対応しています。
1H-NMRの場合は定量性が高いため、積分比を求めることで、同一環境にあるプロトンの存在比を求めることができます。
あくまで相対比なので、等価プロトン多めな対称性の高い構造の場合は要注意です。
また、酸性度の高いプロトンは重溶媒との重水素交換を起こすことが多く、定量性が損なわれるケースが多いことも留意しておく必要があります。
13C NMR
NMRの基礎知識は1H NMRで紹介しました。
ここでは、z,sup>13C NMRと1H NMRの違いを中心に紹介していきます。
13C NMRでわかること
1H NMRでわかるのは、水素の情報です。
それに対して、13C NMRでわかるのは、炭素の情報です。
13C NMRは、主に1H NMRで推定した構造の確認に用いられます。
特に、水素をもたない4級炭素の情報を得るためには有用です。
また、特定の官能基(カルボニル基など)の有無がわかります。
その他、各混成(sp3, sp2 or sp)の非等価な炭素原子の数もわかります。
13C NMRの特徴
13C NMRには以下のような特徴があります。
- 12Cではなく13C
- 1H NMRと比べて感度が低い
12Cではなく13C
炭素の同位体として多く存在するのは、12Cです。
しかし、NMRでは13Cについて測定します。
それは、12Cの核スピン量子数が0であるからです。
13Cの核スピン量子数は1/2であり、NMR測定が可能です。
ちなみに、核スピンをもつ原子は陽子あるいは中性子数のどちらかが奇数の場合を意味します。
測定できる核:1H, 14N, 13C
測定できない核:16O, 12C
感度が低い
13C NMRの測定感度は、1H NMRの測定感度に比べて低いです。
それは13Cの天然存在比(1.1%)が1Hの天然存在比(99.98%)と比べて低いからです。
核の検出感度は、磁気回転比の3乗に比例します。
この解決方法として、高濃度のサンプルを用意したり、測定時間を長くしたりする方法があります。
13Cの実効感度は1Hの実効感度の約1.76×10-4倍
400 MHzNMRで測定する場合、3 mgのサンプルであれば1H NMRが1分に対して13C NMRは12時間 20 mgのサンプルであれば13C NMRで10分に短縮
1H NMRとの違い
共鳴周波数
1Hの場合、B0=11.74 Tにおける共鳴周波数は500 MHzであるが、13Cの場合は125 MHzです。
化学シフトの範囲
13C NMRの測定範囲は0~200 ppmです。1H NMRの測定範囲は―3~15ppm程度であるため化学シフトが一致する場合がありますが、13C NMrでは滅多に起こりません。
スピン多重度の観測
13C NMRでも1Hとのカップリングによるピークの分裂が起こります。
しかし、ただでさえ弱いピークが、分裂することによりさらに弱くなってしまうため、デカップリングという作業を行い、カップリング情報を消去します。
シグナル強度
シグナル強度は炭素数に比例しません。
13C NMRのシグナル強度は、以下の影響を受けます。
- 緩和時間
- 核オーバーハウザー効果
重溶媒のピーク位置
溶媒としてCDCl3を用いた場合、77 ppmに3本の分裂したピークが見られます。
13C NMRの観測
13C NMRではTMSを0 ppmとします。
見た目は1H NMRと類似しており、電子不足は低磁場側、電子豊富は高磁場側にシフトします。
13Cは1Hより遮蔽効果を受けやすいです。
CDCl3の77 ppmと境界として考え、これより低磁場側であればカルボニル炭素、芳香族、オレフィン、高磁場側であればヘテロ原子隣接炭素、単結合炭素となることが考えられます。
DEPT法
13C NMRの特殊測定法として、DEPT法があります。(DEPT: Distortionless Enhancement by Polarization Transfer)
この方法では、炭素の級数によってスペクトルが上下に分かれて観測されます。
よくDEPT Xと表され、このときXはパルスを照射する角度を意味します。
| CH3 | CH2 | CH | 4級炭素 | |
| DEPT45 | ↑ | ↑ | ↑ | - |
| DEPT90 | - | - | ↑ | - |
| DEPT135 | ↑ | ↓ | ↑ | - |
13C NMRのケミカルシフト
等価な炭素は同じケミカルシフト
当たり前ですが、等しい環境に存在する炭素は同じケミカルシフトとなります。
ジクロロベンゼンを測定した場合、3つの異性体(o, m, p体)は等価な炭素数が異なるため、13C NMRによって見分けることができます。
磁気異方性効果・電子密度
13C NMRでは、CH3のシグナル強度がCHのシグナル強度より強くなります。
つまり、プロトンがより多く結合している炭素の方が強いピークとして現れます。
また、カルボニル炭素は電子密度が低いため、かなり低磁場側にピークが現れます。
カルボニルのα位は、共鳴効果よりもメチル基の電子的効果を強く受けます。
アルデヒド・ケトン・エステル・アミド
アルデヒドやケトンのピークは、エステルやアミドのピークよりも低磁場側に現れます。
芳香環電子供与基のイプソ位
芳香環電子供与基のイソプ基は一般にシグナル強度が小さいです。
そのケミカルシフトは置換基に依存します。
ただし、プロトンと比べて明確な影響は受けません。
置換基効果
ハロゲン原子の効果は1Hより顕著に現れます。
IRスペクトル
IRスペクトルでわかること
IRスペクトルでは、分子の振動により官能基がわかります。
具体的には、カルボニル基・ニトロ基・シアノ基の存在を確認できたり、ケトン・アミド・エステルを区別できたりします。
また、カルボニル化合物において、環状か鎖状かを区別することも可能です。
IRスペクトルの特徴
測定方法
IRスペクトルでは、物質に赤外領域の電磁波を照射し、分子の振動遷移に基づく吸収を測定します。
赤外領域とは、波長2500~25000 nmのことなので、波数では4000~400 cm-1に相当します。
波数とエネルギーは比例するため、エネルギーが大きくなると波数も大きくなります。
また、振動遷移とは、振動準位間の遷移のことです。
分子をを振動させるのに必要なエネルギーは、化合物によって異なります。
ある一定の赤外線を当てるとそのエネルギーが分子を振動させることを吸収といいます。
振動の種類
振動の種類には、大きく2種類があります。
「伸縮振動」と「変角振動」です。
変角振動は、さらに面内変角振動と面外変角振動に分けられますが、初めはあまり気にしなくても大丈夫です。
伸縮振動の方がエネルギーが大きいです。
IR九州は、分子中の特定の結合の振動励起と関連付けられます。
振動数・結合強度・換算質量の関係
結合の振動数(波数)は、「球とバネ」モデルを用いて表すことができます。
フックの法則より、結合強度および原子の換算質量と関連付けられます。
特性吸収
特定の置換基は、特定の波長にピークを示します。
これを、その置換基における特性吸収といいます。
ヒドロキシ基の特性吸収
3300~3700 cm-1にO-Hの伸縮振動のピークが現れます。
一般的なカルボニル基の特性吸収
一般的なカルボニル化合物であれば、1550~1800 cm-1にC=Oの伸縮振動のピークが現れます。
ひずみのないケトンであれば1715 cm-1あたりにそのピークが現れ、これを基準にすると考えやすいです。
これより高波数側にピークが現れるカルボニルは以下のような特徴をもっていることが考えられます。
- 電気陰性度の高い原子が結合している(>1730 cm-1)
- 小員環をもっている(5員環:1745 cm-1, 4員環:1784 cm-1, 3員環:1850 cm-1)
- アルデヒド(1730~1740 cm-1)
共役カルボニルの特性吸収
共役カルボニルのC=O伸縮振動は1675~1695 cm-1にピークが現れます。
一般的なカルボニルより低波数側に現れるのは、共役によりカルボニル基の二重結合性が減少しているためです。
カルボン酸の特性吸収
カルボン酸のC=O伸縮振動は1760~1770 cm-1にピークが現れます。
一般的なカルボニルより低波数側に現れるのは、水素結合によりカルボニル基の二重結合性が減少しているためです。
アミド
1663 cm-1程度にC=Oの伸縮振動、1633 cm-1程度にN-Hの変角振動のピークが現れます。
ニトロ基
1521 cm-1程度にN-Oの逆対称伸縮振動、1347 cm-1程度にN-Oの対称伸縮振動のピークが現れます。
ニトリル
~2250 cm-1にC≡Nの伸縮振動のピークが現れます。
FTIR
更新をお待ちください。
UV-Visスペクトル
UV-Visスペクトルでわかること
UV-Visスペクトルでは、非局在化したπ結合の長さがわかります。
共役が伸びるほど、長波長側にシフトします。
UV-Visスペクトルの特徴
測定方法
UV-Visスペクトルでは、物質に紫外・可視領域の電磁波を照射し、分子の電子遷移に基づく吸収を測定します。
紫外領域とは200~400 nmで、可視領域とは400~800 nmのことです。
ここでの吸収は電磁波のエネルギーが分子に移動することを表しており、吸収された波長の色は見えなくなります。
また、測定に用いる溶媒や容器によって結果が異なるのがUV-Visスペクトルの特徴です。
電子遷移の種類
n-π*遷移
カルボニル基をもつ化合物に見られます。
Oの比共有電子対からC=Oのπ*結合への遷移です。
直交した軌道間電子遷移は起こりにくく、モル吸光係数は非常に小さいです。
π-π*遷移
π結合をもつ不飽和有機化合物にみられる最も代表的な遷移です。
この遷移によて吸収されるエネルギーは、HOMO-LUMO間のエネルギー差に相当します。
UV-Visスペクトルで登場する用語
深色移動(red shift):長波長側に移動すること
浅色移動(blue shift):短波長側に移動すること
濃色効果:吸収強度を増大させること
淡色効果:吸収強度を減少させること
ランベルト・ベールの法則
UV-Visスペクトルは、ランベルト・ベールの法則に従います。
ランベルト・ベールの法則とは、吸光度Aは溶液層の長さIおよび試料の濃度cに比例するという法則です。
\[A=\log(\frac{I_0}{I})=\varepsilon cl\]
ここで、イプシロンは比例定数であり、濃度cがモル濃度の場合はモル吸光係数と呼びます。
Massスペクトル
Massスペクトルでわかること
Massスペクトルでは、分子の質量、同位体の構成比を測定することができます。
フラグメンテーションにより分子の形を推測できるのも大きな特徴です。
Massスペクトルの特徴
測定方法
Massスペクトル(MSスペクトル)では、分子をイオン化して磁場の中に入れ(試料導入)、運動するイオンと磁場の相互作用の大きさがイオンの質量と電荷の比に依存することを利用して、イオンに関する情報を測定します。
イオン化・分離をしなければMassスペクトルは測定できません。
イオン化
2個の原子A, Bから成る分子ABに高速の電子を衝突させるとABから電子が弾き出され、分子陽イオンAB+・が生成します。
このイオンは高エネルギー状態にあるので自発的に分解し、陽イオンA+とB・を生成します。
イオンの分離
装置はイオン化室、磁場、フィルムから成ります。
フィルムをマイナスに帯電しておき、高調空中でイオン化されて陽イオンとなったイオン化室の窓を開けるとフィルムに向かって飛んでいきます。
ここで磁場をかけるとフレミングの法則によって、イオンの行路が曲げられます。
その後のイオンの行路の曲げられ方はイオンの質量と電荷の比(m/z:質量電荷比)に依存します。
その結果、フィルムの異なった位置で感光するため、うまく測定できます。
感光した位置をm/z、感光したイオン個数を相対強度で表したものがMSスペクトルです。
代表的なイオン化法
EI法 電子イオン化法
EI法(Electron Ionization)は、前項で述べた方法です。
フラグメンテーションが出やすいハードなイオン化法である一方、分子イオンが検出しにくいです。
そのため、分子量が1000以下の化合物に適しています。
FAB法 高速原子衝突法
FAB法(Fast Atom Bombardment)は、試料とマトリックスをよく混合してターゲット上に塗布し、ArやXeなどの高速中世原子を衝突させてイオン化する方法です。
マトリックスとは、試料分子のイオン化を助ける補助剤です。
直接イオン化しないため、EI法と比べてソフトなイオン化法です。
分子量が3000以下の化合物に適しています。
この方法を用いる場合、適切なマトリックスを選択する必要があります。
ESI法 エレクトロンスプレーイオン化法
ESI法(Electrospray Ionizaiton)は、大気圧イオン化法の一種で、キャピラリに高電圧を印加すると試料溶液が自ら噴霧してイオン化を行う現象を利用した方法です。
フラグメントが得られないソフトなイオン化法です。
マトリックスを必要とせず、分子量が5000以下の化合物に適しています。
MALDI法 マトリックス支援レーザー脱離イオン化法
MALDI法(Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization)は、レーザー脱離イオン化法の一種で、試料とマトリックスの混合結晶を作製してそれにレーザー光を照射することによりイオン化する方法です。
フラグメントが得られないソフトなイオン化法であり、高分子やタンパク質の分析に用いられます。
ただし、適切なマトリックスを選択する必要があります。
代表的なイオン分離法(質量分析計)
MS 磁場型質量分析計
MS(magnetic sector Mass Spectrometer)は、EI法やFAB法によく用いられます。
感度は低い一方、分解能は高いです。
大型であり、試料を多く必要とします。
Q-MS 四重極型質量分析計
Q-MS(Quadrupole Mass Spectrometer)は、ESI法でよく用いられます。
安価・小型・軽量であり、高真空を必要としません。
その代わり、感度や分解能が低いです。
TOF-MS 飛行時間型質量分析計
TOF-MS(Time-Of-Flight Mass Spectrometer)は、磁場を用いて分離せずにイオンの飛行時間を測定する方法です。
軽いイオンの方が重い分子より速く移動する原理を利用しており、MALDI法やESI法によく用いられます。
高価・大型であり、高真空を必要とします。
その代わり、感度や分解能は高いです。
代表的な試料導入法
キャピラリに入れる
EI法によく用いられます。
試料を多く必要とします。(数mg)
ターゲットに乗せる
ターゲットとは、試料を乗せる場所のことえあり、ここでマトリックスと混合します。
試料を少し必要とします。(~1 mg)
溶液のまま用いる
ESI法によく用いられます。
非常に楽であり、試料はほとんど必要としません。(<1 μg)
他の分析法と併せた測定
GC/MS ガスクロマトグラフィー+マススペクトル
GCは試料を高真空下気化させてカラムクロマトグラフィーにより試料の混合物を分離します。
これにマススペクトルを併せることにより、特定のピークがどんな分子量かを分離することなく確認することができます。
反応追跡などに便利です。
イオン化法にはEI法が用いられます。
LC/MS 液体クロマトグラフィー+マススペクトル
LCは液体試料を高圧下カラムクロマトグラフィーにより分離します。
前項の液体版です。
DART法
液体試料やTLCをかざすだけで分子量が得られる、非常に強い分析法です。
ESI法で測定できる化合物は測定できます。