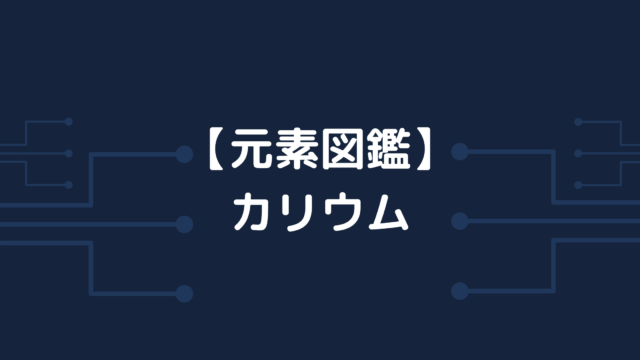【元素図鑑】アンチモン Sb【デジモンに出てきそうな名前】
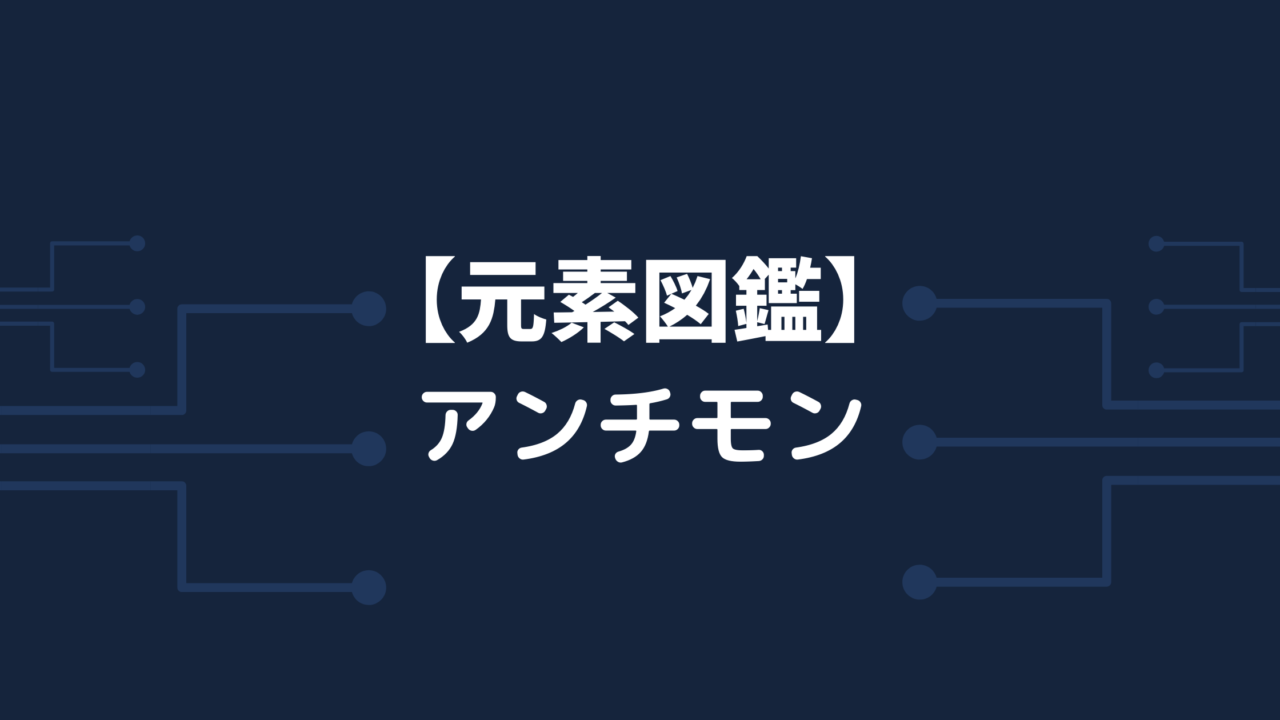
アンチモンに関する情報をまとめました。
アンチモンの基本情報
| 和名 | アンチモン |
|---|---|
| 英名 | Antimony |
| 語源 | ギリシャ語「見出されない(anti-monos)」 |
| 元素記号 | Sb |
| 原子番号 | 51 |
| 原子量 | 121.8 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 白色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 6.691 g/cm3(20℃) |
| 融点 | 630.74℃ |
| 沸点 | 1587℃ |
| 発見者 | 古来より知られている |
| 含有鉱物 | 輝安鉱 |
アンチモンの主な特徴
- 原子番号51の半金属元素で、周期表15族に属す
- 銀白色の結晶性固体で、金属光沢をもちますが、金属としての延性や展性は乏しく、もろく壊れやすいのが特徴
- 熱や電気の伝導性は金属ほど高くありませんが、化学的には金属的性質と非金属的性質を併せ持つ「半金属(メタロイド)」として分類される
- 自然界では主に輝安鉱(Sb₂S₃)として産出され、金属アンチモンとして精製される
アンチモンの歴史
発見
アンチモンの化合物(特に硫化物)は古代エジプトの時代から黒い化粧料(コール)として使用されており、化学的な利用の歴史は非常に古いです。
単体金属としてのアンチモンは中世ヨーロッパにおいて錬金術師たちによって精製されており、文献上では16世紀ごろから明確に記録があります。
名前の由来
元素記号「Sb」は、ラテン語の古名「stibium(硫化アンチモンの意味)」に由来します。
一方、英語名「Antimony」はギリシア語「anti-monachos(修道士の敵)」に由来するという俗説もあり、
古くからその毒性が知られていたことに起因すると考えられています。
アンチモンの主な用途
アンチモンはその合金特性と化合物の機能性を活かして、さまざまな分野で利用されています:
- 鉛との合金: アンチモンを加えることで鉛の硬度を向上させ、バッテリー板・活字合金・はんだ材料に使用
- 難燃剤添加剤: 三酸化アンチモン(Sb₂O₃)はハロゲン系難燃剤と併用され、プラスチックや繊維製品の難燃性向上に寄与
- 半導体材料: Sbはn型ドープ材としてシリコンやGaAsの電子材料に使用される
- ガラス・陶器着色料: Sb化合物は黄や不透明化のために用いられる
- 触媒や合成試薬: SbCl₃などの塩化物は有機合成において脱水剤・ルイス酸触媒として機能
アンチモンの生成方法
アンチモンは以下のようなプロセスを経て製造されます:
- 鉱石の精錬: 主鉱石である輝安鉱(Sb₂S₃)を、鉄と加熱することで金属アンチモンを遊離
- 酸化精錬: 鉱石を空気中で焼成し、三酸化アンチモン(Sb₂O₃)に変えた後、還元
- 電解精製: 高純度なアンチモンが必要な場合は、電解法で精製される
主な生産国は中国が圧倒的で、他にはロシア、ボリビア、トルコなどでも産出されています。
アンチモンを含む化合物
アンチモンは主に+3価および+5価の化合物を形成します。代表的なものには:
- Sb₂O₃(三酸化アンチモン): 難燃剤、白色顔料、ガラスの清澄剤
- SbCl₃(塩化アンチモン(III)): 有機合成でルイス酸触媒や脱水剤として使用
- SbF₅(五フッ化アンチモン): 極めて強いルイス酸。スーパーストロング酸としても知られる
- 有機アンチモン化合物: 一部は農薬や医薬品中間体として利用(現在は毒性のため規制あり)
アンチモンに関わる研究事例
アンチモンに関する研究は、以下のような分野で活発に行われています:
- 難燃性材料の開発: Sb系難燃剤の機構解明と代替物質(ハロゲンフリー)の開発
- 新規半導体材料: Sb₂Se₃などの化合物半導体による太陽電池の研究
- スピントロニクス材料: Sbを含むトポロジカル絶縁体(Bi-Sb系)に関する研究
- 環境分析: 水中のSb汚染の動態解析、分離・除去技術の開発
- 合金設計: Pb-Sb、Sn-Sbなどのはんだや活字合金の構造・耐食性の研究
参考図書
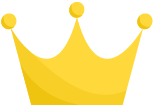 第1位
第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
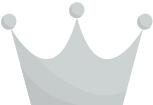 第2位
第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
 ランキング3位
ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。