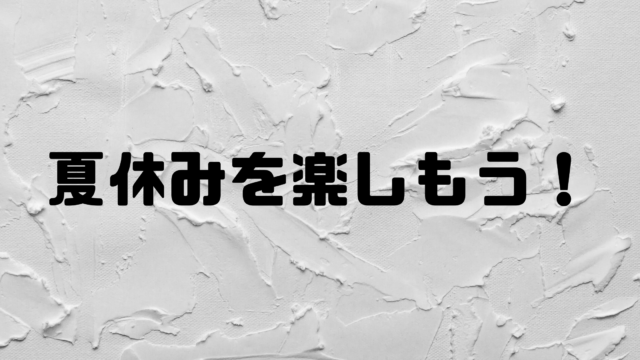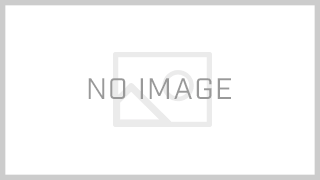【第5章】官能基とは?一覧・構造・覚え方・反応性を体系的に解説
有機化合物の性質や反応性は、分子中に含まれる特定の原子団、つまり官能基(functional group)によって大きく決まります。官能基は「分子の反応の顔」とも言われ、有機化学を学ぶうえで最も重要な知識の一つです。
本章では、代表的な官能基を分類しながら、それぞれの構造・命名法・物理的性質・化学的性質について体系的に解説します。この記事を読むことで、有機化合物の「どこが反応するのか」「なぜその反応が起きるのか」が明確に見えてくるはずです。
あわせて読みたい
Contents
官能基とは何か?
官能基とは、分子内で特定の化学反応を引き起こす性質をもつ原子団のことです。たとえば、アルコールの –OH 基、カルボン酸の –COOH 基などが該当します。
同じ炭素骨格でも、含まれる官能基が異なればその化合物の性質はまったく別物になります。逆に言えば、有機化合物の反応性は、官能基を見ればある程度予測ができるのです。
官能基の分類(一覧)
| 分類 | 官能基 | 構造例 | 代表的化合物 |
|---|---|---|---|
| 炭化水素系 | アルカン、アルケン、アルキン、芳香族 | –CH3, –CH=CH2, –C≡CH | エタン、エチレン、アセチレン、ベンゼン |
| 含酸素官能基 | アルコール、エーテル、カルボニル基 | –OH, –O–, –C=O | エタノール、ジメチルエーテル、アセトン |
| カルボニル系 | アルデヒド、ケトン、カルボン酸、エステル | –CHO, –CO–, –COOH, –COOR | ホルムアルデヒド、アセトン、酢酸、酢酸エチル |
| 含窒素官能基 | アミン、アミド、ニトロ基 | –NH2, –CONH2, –NO2 | アニリン、アセトアミド、ニトロベンゼン |
| 含ハロゲン官能基 | ハロアルカン | –Cl, –Br, –I | クロロメタン、ブロモベンゼン |
官能基の命名法(IUPAC命名)
IUPAC命名法では、官能基の種類に応じて接頭語(prefix)または接尾語(suffix)が決まっています。いくつかの代表例を紹介します。
| 官能基 | 接尾語 | 例 |
|---|---|---|
| アルコール | -ol | エタノール(ethanol) |
| アルデヒド | -al | エタナール(ethanal) |
| ケトン | -one | プロパノン(propanone) |
| カルボン酸 | -oic acid | エタン酸(ethanoic acid) |
| アミン | -amine | メチルアミン(methylamine) |
命名の際は、もっとも優先度の高い官能基を主官能基として接尾語で表記し、他の官能基は接頭語で表すというルールがあります。
官能基の性質と反応性
官能基はその構造によって、電子密度・極性・水素結合の有無・共鳴構造などの要素に影響を与えます。これが反応性を大きく左右します。
アルコール(–OH)
- 極性が高く、水素結合が可能
- 酸性・塩基性の両方の反応を受ける
- 脱水によるアルケン化、酸化によるアルデヒド/ケトン生成などが重要
カルボン酸(–COOH)
- 強い酸性を持つ
- 共鳴構造により、プロトン放出後の安定性が高い
- エステル化反応やアミド化反応など多彩な変換が可能
アミン(–NH2)
- 塩基性が強く、求核剤としても働く
- 置換反応や付加反応の出発点になりやすい
- 第一級~第三級アミンで性質が変化
カルボニル基(C=O)
- 極性が高く、求核攻撃を受けやすい
- アルデヒド・ケトン・カルボン酸・エステル・アミドなど多くの官能基に含まれる
官能基の覚え方のコツ
- グループごとに図解でまとめる(酸素系、窒素系など)
- 語尾の特徴に注目(–ol, –al, –one など)
- 例題で使う(命名法、反応式、構造決定問題)
- フラッシュカードやクイズ形式で繰り返す
まとめ:官能基を理解することは有機化学を理解すること
- 官能基は化合物の反応性・性質を決定づける中心的な構造
- 分類・構造・命名法を押さえることで、全体像が見える
- 反応の起点となるため、今後の章の理解にも直結
次章では、有機反応の基本概念(電子の流れと反応機構)について解説していきます。官能基の理解をベースに、「なぜその結合が切れて、その結合ができるのか?」を電子の視点から読み解きます。