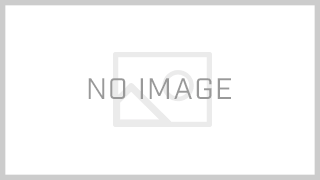ウレア官能基の構造・性質・合成・反応・医薬・材料応用まで徹底解説
ウレア(urea)または尿素は、2つのアミノ基がカルボニル基(C=O)を介して結合した構造を持つ直線型のジアミド類です。
官能基としてのウレアは、医薬品・農薬・高分子・触媒分子などの設計において、水素結合性・安定性・電子的性質を活かして多様に利用されます。
本記事では、ウレア官能基の構造、命名法、合成法、主な反応、性質、応用例などを有機化学的に詳しく解説します。
Contents
ウレアの構造と命名法
基本構造
R₁–NH–(C=O)–NH–R₂- 中央にカルボニル基(C=O)
- 両端にアミノ基(–NH₂ または 置換アミノ基)
命名法
- 最も単純なもの(NH₂–CO–NH₂)は「尿素(urea)」
- R基を持つ場合:「N,N’-ジアルキルウレア」などと命名
命名例
- NH₂–CO–NH₂ → 尿素(urea)
- Ph–NH–CO–NH–Ph → 1,3-ジフェニルウレア
- Me–NH–CO–NH–Et → N-メチル-N’-エチルウレア
ウレアの物理的性質
- 白色固体、融点:133~135℃(尿素)
- 水素結合能が非常に高い(2つのNH、1つのC=O)
- 水や極性溶媒に溶解
- 結晶性に優れ、高融点の物質も多い
ウレアの主な合成法
① ホスゲン法
2 R–NH₂ + COCl₂ → R–NH–CO–NH–R + 2 HCl最も基本的な方法。ホスゲン(COCl₂)を用いてウレア結合を形成。
② イソシアネート法
R–NH₂ + R'–N=C=O → R–NH–CO–NH–R'アミンとイソシアネートの反応。選択性が高く、多用される。
③ ウレア転位反応
- カルバミン酸誘導体や尿素誘導体から誘導的にウレア構造を構築
④ 尿素の直接誘導化
- 尿素に対しアルキル化・アシル化・アリール化などを行う
ウレアの主な反応
① 水素結合形成
- ウレアはHドナー(–NH)およびHアクセプター(C=O)として作用
- 超分子化学、分子認識、酵素模倣で重要な役割
② 脱水縮合反応
- ウレアを含む縮合反応(例:メラミン樹脂の架橋)
③ 分解反応
- 強酸や強塩基下で加水分解され、アミンとCO₂に分解
④ メタル錯体の形成
- ウレアのOまたはN原子が金属と錯体を形成
ウレアの応用
① 医薬品
- ジフェニルウレア構造は抗がん剤・チロシンキナーゼ阻害薬に多く見られる
- 尿素誘導体は利尿薬・降圧薬・糖尿病治療薬にも含まれる
- 例:ソラフェニブ(抗がん剤)、カルバミド(皮膚軟化剤)
② 高分子材料
- ポリウレア:イソシアネート+ジアミン → ウレア結合を持つ高分子
- 耐熱性・機械強度に優れ、塗料・接着剤・エラストマーに利用
③ 農業用途
- 肥料としての尿素:窒素含量が高く、安価で供給源として最適
④ 分子認識・触媒化学
- 水素結合を介した配向制御、アニオン捕捉、触媒設計
ウレアの生体関連と歴史的意義
① 最初の人工有機化合物
- 1828年、フリードリヒ・ヴェーラーが無機化合物(シアン酸アンモニウム)から尿素を合成
- 「有機物=生命に由来」という生命力説を否定した歴史的合成
② 生体内代謝物
- 尿素回路(オルニチン回路)で生成され、窒素代謝の最終産物
③ 脱尿素反応
- アミノ酸合成・ペプチド変換に関与する重要反応
まとめ:ウレアは構造制御・水素結合・生理活性を兼ね備えた多機能官能基
- ウレアはアミドに似た構造であり、2つの–NH基とC=Oを持つ
- 水素結合能が高く、分子間相互作用の設計に最適
- 医薬・材料・農業・超分子化学など広範な分野で応用される
- 歴史的にも有機化学を発展させた画期的化合物
次回は「チオウレア(–NH–(C=S)–NH–)」をテーマに、ウレアとの違い、電子特性、硫黄原子の役割、触媒・材料・薬理応用などを解説します。
🧭 関連リンク
- 👉 【まとめ記事】官能基シリーズ 一覧はこちら
- 👉 【第14回】エナミン官能基
- 👉 【第16回】チオウレア官能基(近日公開)