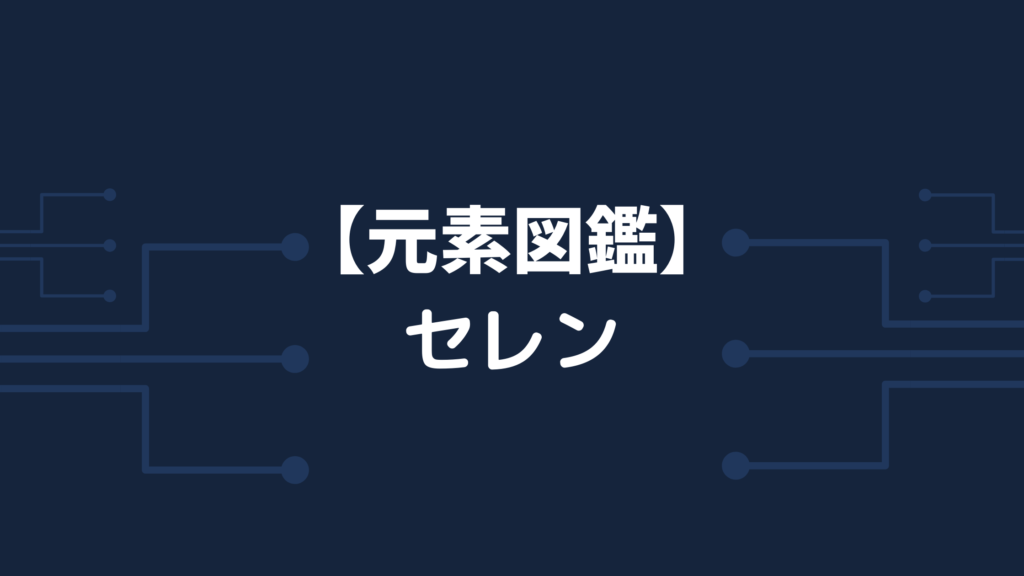セレン(Selenium、元素記号:Se)は、周期表の第16族に属する非金属元素で、原子番号34です。セレンは自然界に広く存在し、さまざまな用途と生物学的役割を持つ元素です。以下に、セレンの基本特性、発見の歴史、用途、化学的性質、生物学的役割について説明します。
セレンの基本情報
| 和名 | セレン |
|---|---|
| 英名 | Selenium |
| 語源 | ギリシャ語「月(selene)」 |
| 元素記号 | Se |
| 原子番号 | 34 |
| 原子量 | 78.97 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体 |
| 色 | 灰黒色 |
| 密度 | 4.790 g/cm3(灰色固体, 20℃) |
| 融点 | 220.2℃ |
| 沸点 | 684.9℃ |
| 発見者 | ベルセーリウス, ガーン(スウェーデン)[1817年] |
| 含有鉱物 | 自然セレン |
セレンの主な特徴
- カルコゲンに属する非金属元素で、硫黄やテルルと同じ族に分類される
- 同素体が複数存在し、灰色(結晶型)、赤色(アモルファス)、黒色などの形で存在する
- 電気伝導性が光により増加する光伝導性を示すため、かつては光電池やコピー機ドラムに利用されていた
- 生体内では微量必須元素として働き、酵素の活性中心(セレノシステイン)として重要
セレンの歴史
発見
セレンは1817年、スウェーデンの化学者イェンス・ベルセリウスとヨハン・ガンが硫酸製造工程の副生成物から発見しました。
当初はテルルと誤認されていましたが、分析の結果、全く新しい元素であることが明らかになりました。
名前の由来
テルル(地球にちなんで名付けられた)に似ているため、地球の惑星して地球と近い関係にある月にちなんで名付けられたという考え方がある。(セレンは周期表上でテルルのすぐ上に位置している。)
他には、この元素の燃える姿が月の青みを帯びた様子に似ているため、月に由来する名前がつけられたという説もある。
セレンの主な用途
セレンはその光学的・電子的特性を活かして、以下の用途に利用されます:
- 整流器・光導電体: セレン整流器、太陽電池、コピー機の感光ドラムに利用(現在はほぼ代替)
- ガラス着色剤: 赤色ガラスや脱色剤として使用
- 合金添加材: 鉛との合金で被削性や耐食性を向上
- 農薬・殺菌剤: 有機セレン化合物が特定用途で使用
- 動物飼料・サプリメント: 微量必須元素としてビタミンEとの相乗効果を期待
工業
セレンはガラス製造において脱色剤や赤色着色剤として使用されます。
電子産業では、光導電性を利用してコピー機の感光ドラムや太陽電池に利用されます。
農業
一部の肥料には微量元素としてセレンが含まれており、植物の成長を促進します。
合金
銅や鉄の合金に添加することで、機械的特性や耐腐食性を向上させます。
セレンの生成方法
セレンは主に銅鉱石の電解精錬過程で副産物として得られます:
- アノード泥処理: 電解精錬の際に生成するアノードスライムから、セレンを酸化・沈殿により分離
- 酸化・還元工程: SeO2として抽出後、還元して単体Seを得る
- 副産物としての回収: 硫酸製造や鉛・ニッケル精錬でも少量が得られる
セレンを含む化合物
セレンは−2価、+4価、+6価など多様な酸化状態を取り、さまざまな化合物を形成します:
- セレン化水素(H2Se): 毒性が非常に強いガス。還元剤・有機合成中間体として
- 亜セレン酸ナトリウム(Na2SeO3): 工業薬品・栄養添加剤として利用
- セレン化亜鉛(ZnSe): 半導体材料。赤外線用光学材料・レーザー発振体
- セレノシステイン: タンパク質中に存在するアミノ酸。酵素活性に不可欠
セレンは酸化物(SeO2、SeO3)、セレン化水素(H2Se)、セレン酸(H2Se4)など多くの化合物を形成します。
研究事例
セレンは材料科学・生化学・環境科学などの分野で研究が進められています:
- セレン含有酵素の構造解析: グルタチオンペルオキシダーゼなどの抗酸化酵素の活性部位解明
- ナノセレン粒子: 抗酸化作用・抗菌性を持つバイオナノ材料として医療・化粧品への応用
- 光機能材料: ZnSeやCuInSe2を用いた太陽電池・赤外線センサーの開発
- 環境毒性評価: セレン過剰・欠乏による水生生物・土壌生態系への影響の評価
- 有機セレン化合物の医薬応用: セレノプロドラッグや抗ウイルス剤候補の合成研究
筆者の薦める1冊
元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。