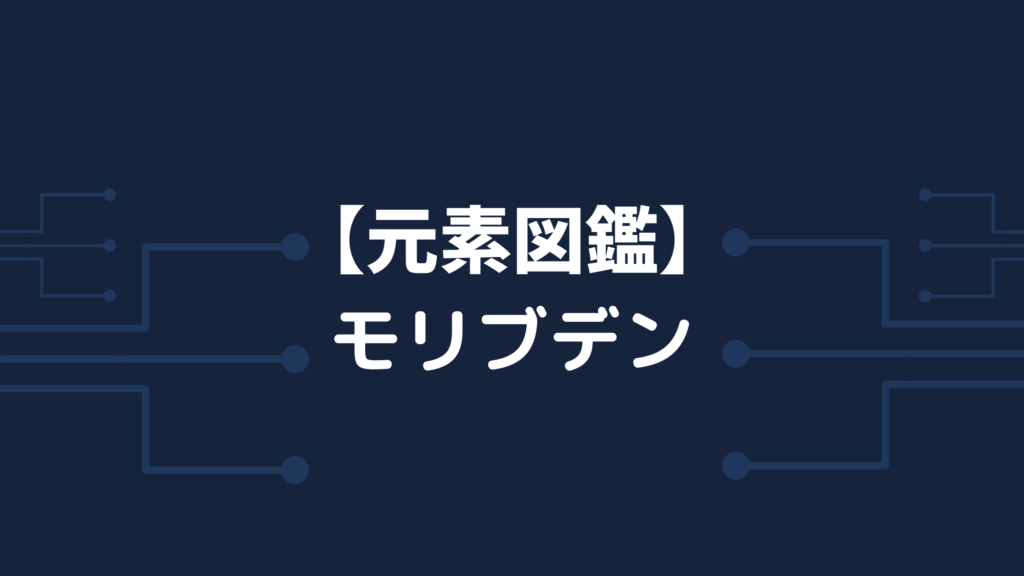モリブデンに関する情報をまとめました。
モリブデンの基本情報
| 和名 | モリブデン |
|---|---|
| 英名 | Molybdenum |
| 語源 | ギリシャ語「鉛(molybdos)」 |
| 元素記号 | Mo |
| 原子番号 | 42 |
| 原子量 | 95.95 |
| 常温(25℃)での状態 | 固体(金属) |
| 色 | 銀白色 |
| 臭い | ー |
| 密度 | 10.220 g/cm3(20℃) |
| 融点 | 2623℃ |
| 沸点 | 5557℃ |
| 発見者 | イェルム(スウェーデン)[1781年] |
| 含有鉱物 | 輝水鉛鉱 |
モリブデンの主な特徴
- 原子番号42の遷移金属元素で、周期表第6族に属す
- 銀白色で高融点(2623℃)を有し、非常に高い耐熱性・強度・耐食性を示す金属
- 生体内では微量元素として必須であり、酵素の補因子としても重要
- 電気・熱伝導性も高く、各種工業材料・化学触媒・電子部品に幅広く利用されている
モリブデンの歴史
発見
モリブデン鉱石は古くから知られていましたが、18世紀まで鉛や黒鉛と混同されていました。
1781年、スウェーデンの化学者カール・ヴィルヘルム・シェーレ(Carl Wilhelm Scheele)が鉱石からモリブデン酸を抽出。
翌年、ピーテル・ヤコブ・イェルム(Peter Jacob Hjelm)が酸化物を炭素で還元することで、金属モリブデンを初めて単離しました。
名前の由来
元素名「モリブデン(Molybdenum)」は、ギリシャ語の「molybdos(鉛)」に由来し、かつて鉛と誤認されていたことにちなみます。
モリブデンの主な用途
モリブデンは以下の分野で多く用いられています:
- 合金添加元素: 鋼に添加して高強度・耐熱性・耐食性を向上(ステンレス鋼、工具鋼など)
- 電子部品: 高融点・導電性により、真空管やディスプレイ用電極、スパッタリングターゲットなどに使用
- 触媒: 石油脱硫・水素化反応用の硫化モリブデン(MoS₂)触媒が代表的
- 航空・宇宙材料: 高温下でも強度を保つため、ジェットエンジン部材に使用
- 化学工業: モリブデン酸ナトリウムなどを顔料・腐食防止剤として使用
モリブデンの生成方法
モリブデンは主に次の鉱石から産出されます:
- モリブデン鉱(モリブデナイト MoS₂):主要な原鉱
- 銅鉱石の副産物: 銅の製錬過程で副次的に回収
精製は以下の工程で行われます:
- 鉱石を焼成して酸化モリブデン(MoO₃)に変換
- 水素などを用いて還元し、金属モリブデンを得る
モリブデンを含む化合物
モリブデンは多様な酸化数(+2〜+6)を取り、さまざまな化合物を形成します。
主なものは以下の通りです:
- MoO₃(酸化モリブデン): 白色の粉末。顔料・腐食防止剤・触媒原料に使用
- MoS₂(硫化モリブデン): 黒色の固体で、潤滑剤や脱硫触媒として使用される
- モリブデン酸塩(MoO₄²⁻): 水溶液中ではモリブデン酸ナトリウムなどの形で存在
- Mo(CO)₆(六炭化モリブデン): 揮発性の金属錯体。有機金属反応やCVDに使用される
モリブデンに関わる研究事例
モリブデンは基礎研究から応用研究まで幅広く対象とされています:
- 水素発生触媒: MoS₂を基盤とする非貴金属触媒の開発
- 2次元材料: MoS₂の単層膜は、グラフェンに続く次世代電子材料として注目
- 高温材料開発: モリブデン合金の耐酸化被膜技術に関する研究
- 生物学的役割: モリブデン酵素(硝酸還元酵素など)における活性中心の構造解析
- 有機金属化学: Mo触媒によるアルキンメタセシス反応の開発
参考図書
元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。
これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!
リンク
この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。
「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。
理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。
リンク
実は鉱石好きだった宮沢賢治。
教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。
リンク